2020/04/22
青柳 将人 文教堂 教室事業部 ブックトレーニンググループ
『あの人のこと』河出書房新社
久世光彦/著

久世さんが姿を見せなくなってからもう十四年が経つ。
当時は未完のまま刊行された『百閒先生 月を踏む』(朝日新聞出版社)を読む気持ちにはなれず、未読の作品を棚に残すことで久世光彦という作家の著作を心の内で完結させないようにしていた。
ところがどうしてだろう。数年に一度の間隔で久世さんの新刊が発売されているのだ。
シンプルなうす水色の表紙に久世光彦と名前があって、気になって手に取ってみれば『あの人のこと』銘打っている。とても久世さんらしい書名だと思った。それと同時に、とても厭らしい書名だ。寺山修司さんも何十年経った今も尚、刊行物が後を絶たないが、久世さんも同じように、目を細めて書店の棚の背表紙を追っていると、そっと顔を出してくるから厭らしくて可笑しいのだ。
今までに刊行されている単行本に収録されていたエッセイや寄稿文に加えて、雑誌や地方紙、小冊子に寄稿した文章が収録されている本書は、役者やタレント、映画監督、作曲家といった、様々な分野で活躍している人達について書かれたエッセイだ。
冒頭の「特別な人」と題された項目では、20年以上に渡って付き合いのあった盟友、向田邦子さんについて書かれている。森繋久彌さんに弟子入りして以来、長く苦楽を共にしてきた久世さんにとって、向田さんは紛うことなく「特別な人」であっただろう。
その後に続く「あの人」達も、樹木希林さんや沢田研二さん、小林薫さんと、久世さんの演出する作品に欠かすことのできない役者が並ぶ。
本書の中でも、特に際立つのが樹木希林さんの旦那様である内田裕也さん。内田さんと希林さんの夫婦喧嘩の仲裁に久世さんが駆け付けた際のやりとりが、殺伐としながらも非常に滑稽で面白い。
「亭主はひたすら怒鳴り、女房は泣きながら、その合間に寸鉄人を刺すような、痛烈な一矢を放つ。
~中略~
九時になると、テーブルを挟んだ二人の間の電話が鳴る。一般社会の始業時である。雌獅子が受話器を取る。いままで泣き叫んでいたのが嘘のように、女房は愛想よく、
「あ、例の物件ね、あれ、もう少しキープさせてくれません?」
相手は不動産業者である。女房の実益を兼ねた趣味は、不動産の売買だったのである。折しも、部屋に燦々と朝日が射す。三人はガックリ白ける。」
頭の中で裕也さんと希林さんが活き活きと動き始める、久世さんが演出するドラマのワンシーンのような素晴らしい文章だ。
久世さんは短い文章の中にも色や表情を付け、時には艶を出して色気を醸し、時には情を語って涙を誘う。そんな言葉を巧みに操る魔術師が、森繋久彌さんについて書かれた項の中で文章を書くことに触れている。
「話言葉には、リズムがある。おなじように、文章にも、リズムがある。繰り返し、繰り返し口にすることによって、生まれてくるテンポとリズムというものがある。森繋さんは、文章を書くとき、かならず声にしながら書く。あるところまで書いたら、また最初から読み返す。どんな長い文章でも、そうする」
こうして生まれたのが、本書の江戸川乱歩について書かれた項でも触れている処女小説『一九三四年冬 ―乱歩』だ。この小説は、江戸川乱歩が実際にスランプで失踪をした空白の期間を元に、江戸川乱歩を主人公にして描かれた作品だ。この作品の中で久世さんは、江戸川乱歩に扮し、作中で『梔子姫』という作品を生み出す。
その後の著作でも『謎の母』(新潮社)や『蕭々館日録』(中央公論新社)、『陛下』(中央公論新社)等の作品で実在していた作家や人物を緻密に描写し、妖しくも美しい、独特の作品世界を生み出してきた。
また、久世さんは死を予感させる風景を、様々な作品で描き、文章で語っていた。
「人が死ぬのは当たり前のことだ。けれど、その姿はさまざまだ。昨日元気だった人が、今日はもういない。年の順でもない。部屋の中に、ポッカリ一つ空席ができて、その後、誰がそこに坐っても、どうにも落ち着かない。生きているということは、周りに空しい空席が次々とできることなのか。ということは、自分にだっていつか、席を立っていく日がくるのだ」
久世さんが席を立つ日はあまりにも突然で早すぎた。その最後の日の様子については『死のある風景』(新人物往来社)の巻末に、「うす水色の空に」という題で奥様の久世朋子さんが記していて、最後の日は、うす水色の空が拡がっていたというから、本書の表紙と本体がうす水色一色で染められているのは、もしかしたらそれと関係があるのかもしれない。
本書で久世さんの美しい日本語を読んでいると、こうして久世さんの作品を拝読できる日は、そう遠くないのかもしれないと思うから不思議だ。
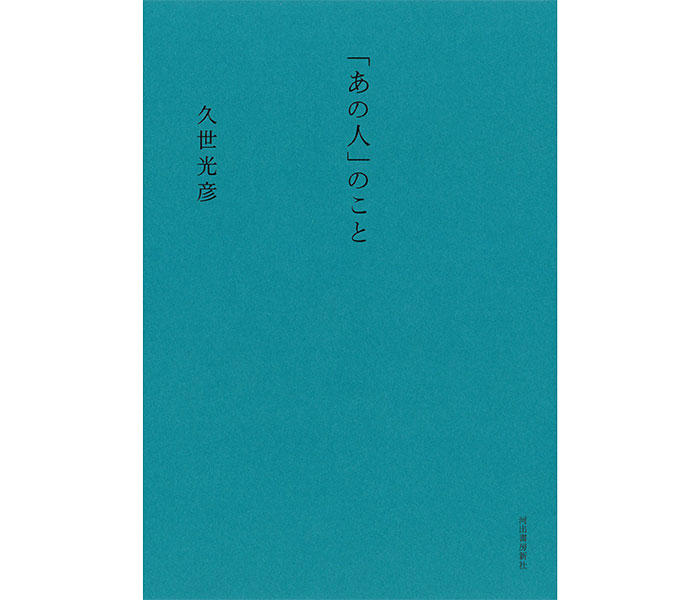
『あの人のこと』河出書房新社
久世光彦/著

