2020/04/30
藤代冥砂 写真家・作家
『西への出口』新潮社
モーシン・ハミッド/著 藤井光/訳
タイトル買い、をたまにする。
「西への出口(原題exit east)」という気負いのない、文学臭の希薄なタイトル。そして著者は、パキスタンとインドの国境の街ラホール生まれで、ロンドン、ニューヨークを行き来しながら暮らしている、らしい。裏カバーに記された粗筋には、戦火の街で恋に落ちた若い男女は、自由への「扉」を探し求める、とある。もうこれだけで、スイッチが入った。
とはいえ、恋愛小説を読むためというよりも、戦火の街でのあれこれを、若い人たちの目を通して体験したかったというのが、スイッチオンの理由だと思う。
なぜ?と聞かれても、うまく答えられない。西にある出口へと主人公らと共に向かいたい。ただそれだけ。理由を作るならそういうことだろう。
読後の印象の半分は、意外なものを読んだ驚きに占められている。なんとなく、レジスタンス、バイオレンス、ラブ、冒険、涙、運命、を予想していただけに、無駄な装飾や舞台説明を極力省いた、機能的なスタイルは、ミニマルとかとは違う意味で、スタイリッシュであり、とはいっても、お洒落ではなくて、手に馴染む美しいドイツ製のペンのようだ。
最初の舞台は中東のどこかの街であるが、地名はない。だが、次の舞台は、ギリシアであり、さらにロンドンへ、カリフォルニアへと西へ西へと転々とする。匿名と実名が混在する土地の登場は、この物語を象徴しているかもしれない。
ノンフィクションとファンタジーが入れ替わりながら、進む物語に、いつしか彼らの困難な旅が、希望の光を灯し始めていることに気づく。その希望とは、この物語内に限定されたものではなくて、ページから越境して、こちらの現在へと乗り込み、この世界の不安定な未来へのトーチライトのようにも思えてくる。
私たちが間違いなく迎えてしまう混乱した未来の中で、新しい世界を望む者たちは、どんなふうに生きていけるのかを見せてくれている。この本もまさに、今読まれるべきなのかもしれない。
この物語では、西への出口が、まじかよ、という現れ方をする。その非現実性は、裏返ったリアルであり、その扉を開けるか開けないかは、それぞれの意志だけに左右される。
私は、その時が来たら、西への出口を使って、新しい世界へと旅立てるのだろうか。答えはすでにある。ただ、一人ではその出口を越えないだろう。誰かの手をとって、もしくは誰かに手をとられて、西への出口へ入ろうと思う。
考えてみれば、人という種族は、かつて旅する民であった。生まれながらの越境者であり、人類の歴史をみればわかるが、定住といのは、つい最近のことだ。
出口を開けておく。これはとても自然なことだと思う。そこは避難ルートとして使うこともあるだろうが、その出口はきっと希望とも読まれることだろう。
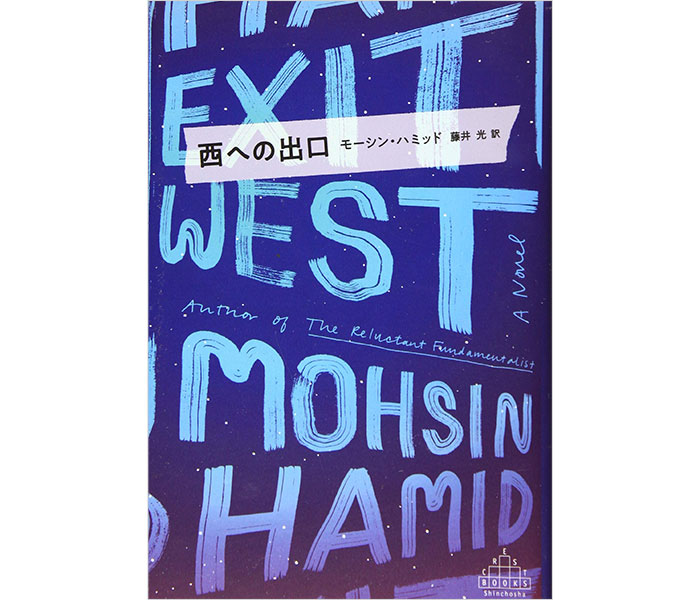
『西への出口』新潮社
モーシン・ハミッド/著 藤井光/訳

