2020/10/13
長江貴士 元書店員
『14歳からの哲学入門』河出書房
飲茶/著
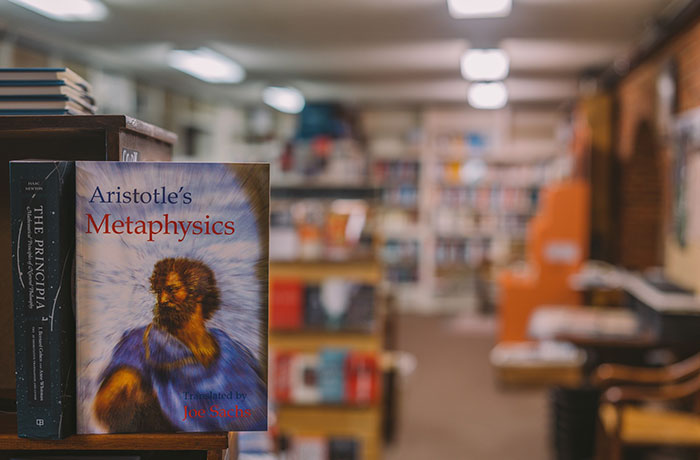
あなたは「哲学」というものを、どんな学問だと感じているだろうか?
僕は元々理系の人間で、だから学生時代にカントだのヒュームだのと言った人たちの考え方に触れた経験はない。難しそうなイメージがあって(実際に難しいのだろうが)、そういう人たちの本を好んで読むこともしなかった。そんな僕が「哲学」に対して抱いていたイメージは、
「偉い人が難しいことについて難しいこと言ってるんでしょ」
程度のものだった。
その後、興味を持つようになって、「哲学」に関する本を読むようになった。とはいえ、やはりすんなり理解できたわけではない。それについて本書の著者である飲茶氏が『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』という本の中で、テレビドラマに喩えて説明している。西洋哲学を難しく感じるのは、テレビドラマの途中だけ見ているからだ、と。西洋哲学には流れがあって、基本的には前の世代の哲学者の主張を受けて新しい哲学が生まれていく。だから、何故その時代にその哲学者がそんなことを言ったのかを理解するためには、全12話のドラマの5話だけ見ても理解できないのと同じように、初回からちゃんと順を追わなければいけないのだ、と。
実際に、西洋哲学について書かれている飲茶氏の『史上最強の哲学入門』は、その思想に貫かれて書かれており、全体の流れが非常に理解しやすかったし、これまで読んだ哲学書と比べて格段に面白かった。それでもやはり、僕にとって「哲学」というのは、「自分に関係のある事柄」だとは思えないままだった。
しかし本書を読んで、その考え方が変わった。本書は、「哲学」というものが実は僕らの人生に大きく関わり得るのだ、ということを明快に示してくれた作品だ。しかも、若い世代であればあるほど、それこそ14歳前後の人であるほど、「哲学」は重要になるのだ、と。
何故か。
[14歳というのは]それゆえに自分でものを考えて「自分なりの価値観」を構築していくべき時期でもあるわけだが、実は、こうした時期において一番学ばなくてはならないものが「哲学」である。なぜなら哲学とは、
「古い常識を疑って今までにないものの見方を発見し、新しい価値観、世界観を創造する学問」
であるからだ。
「哲学」は、時代の閉塞感や人間関係の煩わしさなんかに嫌気が差し、しかし自分の力ではまだ現状を打破することは出来ないような子どもが、せめて思考の中だけでも現状を突破出来るようにするための最良のツールなのだ、と。
しかしそう言われても、カントだのデカルトだのといった「凄そうな人たち」と同じようなことが出来るとは思えないだろう。しかし、まさにその点こそ、本書で最も強く主張される部分なのだ。本書から引用しよう。
ただ勘違いしないでほしい。それほどの哲学を生み出せたのは、彼らが特別賢かったからではない。実際はその逆。彼らの多くは「十四歳レベルの発想」の持ち主であり、むしろそうであったからこそ当時の常識を乗り越えることができたのだ
そう、本書の背後にある真の主張は、「哲学者はただの中二病だ」という点にある。彼らは確かに、それっぽいことをそれっぽい風に言っているし、偉そうに難しそうな言葉で色々語ってはいるが、彼らが主張しているその中身を丁寧に読み解いてみれば、それはただの「十四歳レベルの発想」でしかない、ということを明らかにしていくのが本書なのだ。
タイトルの「14歳」も、そういう文脈で解釈されるべきだ。本書にも、そう書かれている。
本書で語りたいことはまさにここにある。本書は、いわゆる十四歳本のひとつであるが「十四歳のあなたたちがこれから生きていくために有用な哲学を教えますよ」という本ではない。また、「十四歳向けという名目で難解な哲学を子供でもわかるレベルまで噛み砕いて書きました、どうぞ十四歳以上の方も安心して読んでください、ていうか何歳だろうと買え」という本でもない。本書が伝えたいことは、すべての哲学は、十四歳レベルの発想、誤解を恐れずに言えば、「極端で幼稚な発想」からできているということ。どんな哲学書も難解そうに見えて、その「難解な部分(あらゆるツッコミを想定して専門家向けに厳密に書かれた部分)」を取り払ってしまえば、根幹にあるのはこの程度のものにすぎないということだ。
本書は、歴史に名だたる偉大な哲学者たちを十四歳の子供と同レベルだと断ずる本である。それは、哲学のハードルを下げて「哲学って本当は簡単なんですよ」などと言うためではない。哲学とは、もともと、幼稚な発想や誇大妄想のコジツケを「臆面もなく主張する」ことによって成り立っているものであり、十四歳頃に誰もが味わう「常識の崩壊」を乗り越えるためのものであるということを強く訴えたいからである
そこまで哲学書をたくさん読んでいるわけではないが、今までそんな主張をする本に出会ったことがなかったから、本書のこのスタンスは実に新鮮だと感じた。そして、このスタンスに則って本書は書かれているから、全体として非常に読みやすい。一箇所、「デリダって哲学者はめっちゃ難しい文章書くんですよ」という実例として引用されている文章があり、それはまったく理解できなかったが、それ以外で難しいと感じる箇所はなかった。「哲学」というものに人生に一度も触れたことがなく、哲学者の名前なんて一人も知らない、という人が本書を手に取っても、最後まで面白く読み通すことが出来るだろう。
本書ではとにかく、「古い時代の価値観なんか問答無用で捨て去るしかない」という感覚が貫かれている。「哲学」というのは、まさにそうやって進んできた学問なのだ、と。しかし本書では、もう「哲学」は終わってしまった、とも書かれている。その理由は是非本書を読んでほしいが、その「哲学」が終わってしまった世界の中で、じゃあどんな考え方が世の中に現れるべきかという話に続けて、本書では「ニート」が取り上げられている。「働かなければダメだ」という、誰もがあまり疑っていない絶対的な価値観に逆らい抵抗し続けるニートこそ、これからの新しい「哲学」を生み出す存在かもしれない、と本書では書かれている。
大げさだと思うだろうか?実はそうでもないのだ。何故なら、あのニーチェも実際のところただのニートだったからだ。壮大で後世に残る偉大な考え方を提示したニーチェだったが、しかしその彼はその実ニートだった。しかしいいのだ。ニートだろうがなんだろうが、新しい価値観を提示でき、後世まで語り継がれるようになれば勝ちだ。
現代社会は、様々な問題を抱えている。それらを、旧時代の価値観を捨て去ったニートたちがあっさり解決する時代がやってくるとしたら、それはそれで楽しいではないか。

『14歳からの哲学入門』河出書房
飲茶/著

