2020/09/01
るな 元書店員の書評ライター
『小説のストラテジー』筑摩書房
佐藤亜紀/著
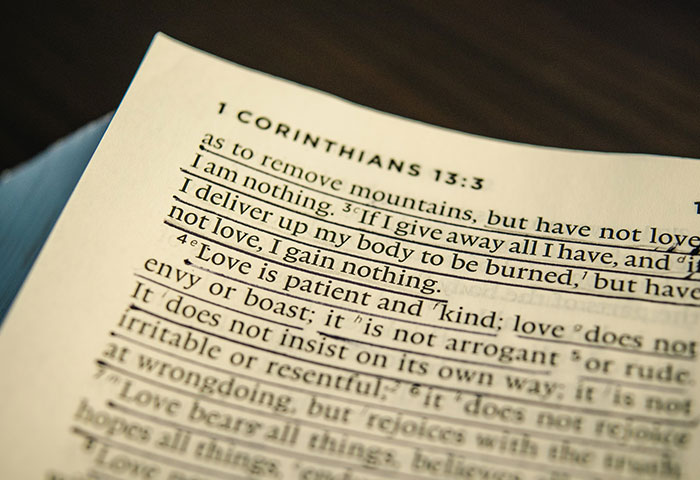
文学とは何か、小説とは何か。それは言語を使った芸術作品である。ならばその時文学は、誰しもが理解できるものである必要はない。なぜなら、絵画、彫刻、音楽…などの芸術は、しばしば私たちの理解を超えて存在するからだ。だから、一体この絵には何が込められているかと、鑑賞者は積極的に干渉しなければならない。作者のバックグラウンド、作られた時代背景などを駆使して汲みとらねばならない。
常日頃、言葉は発した瞬間に、自分の世界の意味を離れて受け取る側の世界の言葉になると思っている。私が発した言葉に感動する人もいれば、気に入らない人もいる。それはこんなに小さなスマホの画面という小窓でも起きるのだから、現実世界ではなおさらだ。言語は意思伝達のツールだから、どうしたってそこには書き手や読み手、話し手と聞き手の主観が入る。視覚、聴覚、色覚、触覚などの感覚器は、物を識別して在るものと認識する程度にしか日常的には必要ではない。電話の音か呼び鈴か、熱いか冷たいかぐらいがわかれば良いのだ。では、芸術作品を鑑賞する場合はどうか。本書はそこから入っていく。
初っ端からヴェロネーゼやカナの婚礼の絵画鑑賞の話。
絵画に疎い私、その理由と絵画の見方が第1章であっという間に解決された。まずここで呆気にとられる。なんやこの人、やっぱりバケモンか。その後も本書は次々と、物語と小説の在り方、読み手の心構えを論じていく。
はっきり言って難しい。でも面白い。ここで言う面白いとは、面白おかしいほうの意味ではなく、一度でも文学を枠組みとして捉え、それが歴史の中でどう生まれ、どう展開してこれからどうなるか?みたいなことを考えたことがある人なら、こんなに面白い本はないと言う意味においてのほうの意味。interestに近い。
その中でも私は特に、小説における物語と記述、言語使用のあたりはぼんやりと疑問に思っていたので、読後は憑き物が落ちたようにスッキリした。
そして、文学が言語芸術である時、読み手は読む都度にその作品を再編して新しいものに造り上げると同時に自分自身の言語体系を更新することになる。言語芸術とは読み手に対するそうした挑戦であり、読み手はその挑戦を受けて作品を読み替えつつ自分自身の言語を変質させる。そこに言語芸術享受の創造性がある。このギャップこそ、創造性を生み出すものだ(本文より抜粋し要約)。
このくだりが、私も思うことと同じだった。
言葉は、放った瞬間その人の世界の言葉の意味に変わってしまう。
通常の小説を読むという行為は、1冊の本を読み、理解して書き手の世界の言語体系を知り、自分を再構築することだが、ならば理解ができなかった時にこそ、その本には芸術性があると、佐藤亜紀は言っているのではないか。
芸術とは、万人誰しもへは理解される必要はない。文学だってそれで構わない。読むという行為が必ず理解へ帰結する必要はないのだ。それが「小説を鑑賞する」ということ。
理解ができない本に出会った読み手は挑戦する。読み方を変えて作品に挑む。芸術とは、時に対峙する己の世界をかけた、思想と思考の戦いなのだ。
読後は、返事に困ったLINEの返事をする時でさえ、言葉の字面と上辺を追うな、テキストを読めと言う佐藤亜紀の声が聞こえてくるようだった。これぞ娯楽を飛び越えた、究極の娯楽としての凄まじく正直で、圧倒的知識と理論、佐藤節が炸裂した小説論。
私にとっては彼女の小説が、「文学は言語を使った芸術である」と実感する瞬間だ。
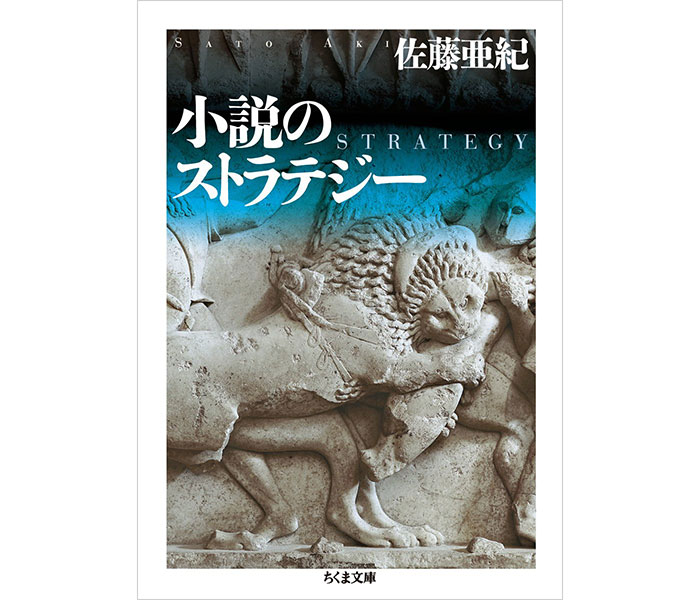
『小説のストラテジー』筑摩書房
佐藤亜紀/著

