2021/02/26
馬場紀衣 文筆家・ライター
『万物創生をはじめよう 私的VR事始』みすず書房
著・ジャロン・ラニアー 訳/谷垣暁美

本書は、第一次VR(バーチャルリアリティー)ブームの立役者である著者が、VRの歩みと来歴、そして次世代への展望をあますことなく書き尽くした一冊。
いったい、こんな時代が来るなんて数十年前には誰が想像しただろう。本書を読んでいて気付かされるのは、VRは私たちが想像する以上の可能性を秘めているということ。VRはまごうことなき「私たちの時代の科学・哲学・技術におけるフロンティア」で、VR科学者は科学の幻術使いなのだ。
著者によれば、理想的なVRの枠組みというのは、感覚運動の鏡であることらしい。VRの視覚的要素が上手く働くためには、バーチャル世界を見まわした時に何が映るのかを計算する必要があるという。
「あなたの視線が漂うとき、VRコンピューターは、バーチャル世界が本物であるとしたら、あなたの目が見るであろうグラフィック・イメージを、つねに、そしてできるだけ迅速に、計算しなくてはならない。あなたが右方に目をやれば、バーチャル世界は、その埋めあわせとして、左方に回転しなくてはならない。そうすることで、バーチャル世界が静止していて、あなたの外側にあり、独立しているという錯覚をつくりだすのだ」
こうした感覚は経験してみないと理解するのが難しそうだ。というのもVRは主観に依拠してのみ存在するので、VRのなかで、もっぱら観察者でいるということは幽霊でいるのと同じことなのだという。それも、化けて出ることも叶わない、下っ端の幽霊らしい。
本書で著者が強調するのは、もしVRの可能性が拡がり、私たちの利用できるシステムが進化したとしても、重要になるのは人間(ユーザー)の身体だということ。未来ではロボットがすべての仕事をするようになる、という考え方をする人もいるかもしれないが、ロボットは実際には自分だけでは何もできないし、人と離れてしまえば存在することすらできない。
著者はさらに、VRはこれまで私たちが経験してきたすべてのメディアと同じく、人間の良いとことも悪いところも増幅すると指摘する。人間の素晴らしい感情移入と共感に結びつくこともあれば、人間ならではの悪質な側面を露見させてしまう可能性もある。それが良いか悪いかは別として「VRの中で新しい身体をつくりあげるとき、私たちは脳も拡張しているのだ。このことがVRという冒険の中心になっていく」という言葉からは、VRによってもたらされる経験は、まだまだ私たちの想像を超えてくるかもしれないという好奇心をかきたてる。
誰もがバーチャルな空間と現実世界にまたがって生活できる時代がすぐそこまで来ている。そんな時代に問いかけるようにして、著者は本書を次のように結んでいる。
「テクノロジーを深く、十分に楽しむこと。それがテクノロジーに所有されるのではなく、テクノロジーを所有するための最善の道だ。さあ、新しい世界に飛びこもう。」
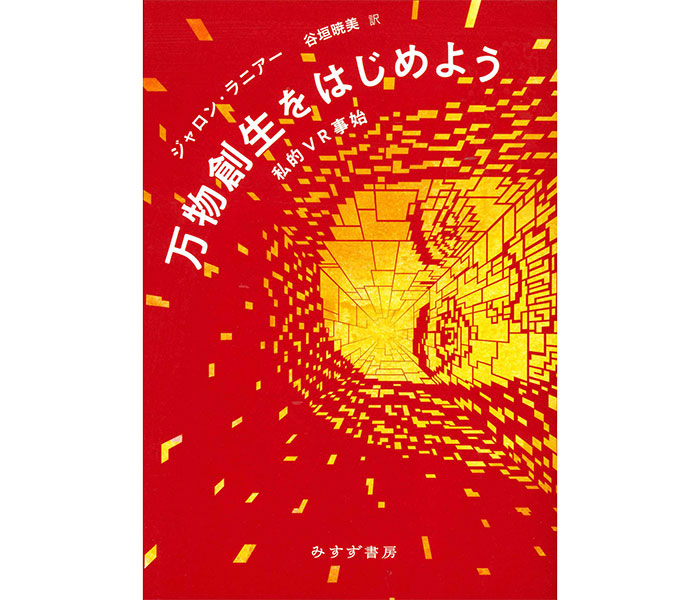
『万物創生をはじめよう 私的VR事始』みすず書房
著・ジャロン・ラニアー 訳/谷垣暁美

