2018/06/28
長江貴士 元書店員
『宇宙は「もつれ」でできている 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか」』講談社
ルイーザ・ギルター/著 窪田恭子/翻訳
史上最も有名な物理学者がアインシュタインであることに、異論がある人は多くはないだろう。舌を出したファンキーな写真も有名だし、原子爆弾との関連で名前を知っている人も多いかもしれない(とはいえ、アインシュタインは原子爆弾の開発とは無関係だったようだが)。
当然だが、物理学の分野においても神がかった成果を残している。「奇跡の年」とも呼ばれる1905年から数年の間に、アインシュタインはその後の物理学の発展に重要な貢献をもたらす論文を5つ発表した。その中には、後にノーベル物理学賞を受賞することになる「光量子仮説」「光電効果」、また発表当時3人しか理解できなかったというエピソードさえある「相対性理論」も含まれる。しかもそれらの論文を発表した当時、アインシュタインは特許局に勤めており、いわば在野の研究者だった。どれほどとんでもない人物であるのか理解できるだろう。
そんなアインシュタインが、生涯認めなかった理論がある。それが、「相対性理論」と並んで20世紀の二大物理学とも呼ばれる「量子論」だ。量子論は現在では、「史上最も成功した物理理論」とも呼ばれており、量子論を応用することでトランジスタや半導体が生み出された。量子論が発展しなければ、テレビもコンピュータもスマートフォンも生まれなかったかもしれない。
そんな量子論を、「神はサイコロを振らない」という有名な言葉で批判したのが、アインシュタインなのだ。量子論というのは、原子などの非常に小さな物質に当てはまる理論だが、この理論は、小さい物質の「位置」は「確率」でしか分からない、と理解されている。つまり、「◯◯という場所にいる確率は81%」「☆☆という場所にいる確率は26%」という具合に、「位置」が「確率」でしか分からない、というのだ。アインシュタインは、サイコロを振るみたいに確率でしか位置が分からないような理論は「不完全」なものだ、と考え、量子論を生涯受け入れなかったという。
相対性理論はアインシュタインがほぼ独力で作り上げた理論だが、量子論は数多くの物理学者の議論や発見や努力が積み重なって確立された理論だ。だからこそ、関わった物理学者によって様々な立場がある。その中で最も有名で、現在でも多数派とされているのが、ボーアが提唱した「コペンハーゲン解釈」と呼ばれるものだ。アインシュタインはこの「コペンハーゲン解釈」に異議を唱え、ボーアと始終激しくやりあったという。
そんなアインシュタインは、結果的に量子論の発展に貢献することになった。その奇妙な軌跡を描き出すのが本書だ。
アインシュタインは、量子論を「不完全」だと考えていた。だから、どうにかしてこの理論に矛盾を見出そうとした。そして考えついたのが、後に「EPRパラドックス」と呼ばれるようになる、とある思考実験だ(アインシュタインは思考実験が得意で、相対性理論を思いついたのも、「鏡に向かって自分が光速で走ったら自分は鏡に映るだろうか?」と考えたことがきっかけだった、というエピソードがある)。アインシュタインが「EPRパラドックス」によって「理論の矛盾」として提示した「エンタングルメント(もつれ)」という状態は、実際に存在することが理解されるようになり、「もつれ」とは何なのかを研究することで量子論が発展していったのだ。本書は、僕らの日常感覚から大きくかけ離れた様々な事実を提示する量子論が、どのように生まれ、どう発展し、どう理解されていったのかを、アインシュタインが持ち出した「もつれ」という概念を中心軸に据えながら描き出していく一冊だ。
では、「もつれ」とは一体何なのか。これを簡単に説明するのは非常に難しいのだが、二つのボールを例にとって説明してみよう。
上空を、二つのボールが飛んでいるとする。この二つのボールには、「一方は赤であり、もう一方は青である」という関係がある。二つのボールは、あまりにも速く飛んでいるので肉眼ではその色は認識出来ないが、特殊なカメラで撮影すると飛んでいるボールの色が分かる、としよう。
さて、この二つのボールを使って、まずアインシュタインの主張とボーアの主張(つまり「コペンハーゲン解釈」)を理解しよう。
アインシュタインは、この二つのボールに「一方は赤であり、もう一方は青である」という関係があるのなら、片方のボールは「常に赤」であり、もう片方のボールは「常に青」だと主張する。まあこれは、非常に受け入れやすいというか、当たり前というか、それ以外の可能性なんかないだろう、という捉え方である。
しかし「コペンハーゲン解釈」は違う。ボーアは、この二つのボールは、観測するまで(この例の場合は、カメラで撮影するまで)それぞれのボールは色が決まっていない、と主張する。つまり、このボールは、カメラで撮影していない時は「何色でもない」という状態であり、カメラで撮影して初めて「赤」か「青」かが決まる、というのだ。ンなアホな、という説明だが、とにかく「コペンハーゲン解釈」上の理解はこうなのだ(もちろんこれは、原子などの非常に小さな物質の場合であって、実際にはボールのような大きさのものには当てはまらないのだが)。
さて、もう一つ理解しておくべきことがある。それは、「情報は光よりも速く伝達することは出来ない」という制約である。これはアインシュタイン自身が「相対性理論」の中で打ち出した考え方で、物理理論が守らなければならない絶対的な制約なのだ。
さて、ここでEPRパラドックスの出番である。アインシュタインはこういう思考実験を考えた。
【「コペンハーゲン解釈」が主張するような、カメラで撮影するまでは色が決まっていない二つのボール(「一方は赤であり、もう一方は青である」という関係がある)を、正反対の方向に飛ばす。そして、お互いの距離が、光の速度でも充分な時間が掛かるほど離れた時に、一方のボールをカメラで撮影したとする。その結果、「赤」だと分かったとしよう。するとその瞬間、もう一方のボールの色が「青」だと分かる(両者には「一方は赤であり、もう一方は青である」という関係があるからだ)。両方のボールの距離は相当に離れているのに、一方のボールの色が「赤」だと分かったその瞬間に、もう一方のボールの色が「青」だと分かるのは、情報が光速度を超えていることになり、矛盾するのではないか?】
この、一方の情報が分かった瞬間に他方の情報が分かる(お互いがどれだけ離れていても同期して振る舞っているように見える)という状態が「もつれ」と呼ばれている。この「もつれ」を理解することこそが、量子論の発展に繋がっていくことになるのだ。
この「もつれ」は、単なる学問上の対象ではない。なんと、実用化される可能性があるのだ。それが「量子コンピュータ」だ。名前ぐらいはよく耳にするだろう。「量子コンピュータ」はまさに「もつれ」を利用した仕組みで成り立っているのだ。そう考えると、アインシュタインの提示した「もつれ」の重要性が少しは伝わるだろうか。
「量子コンピュータ」が実用化されれば、僕らの生活は激変する。またその話は、どこか別の機会で書くことにしよう。
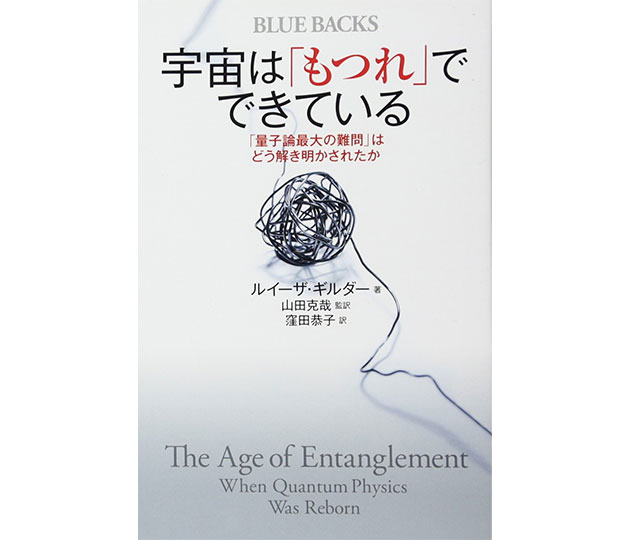
『宇宙は「もつれ」でできている 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか」』講談社
ルイーザ・ギルター/著 窪田 恭子/翻訳

