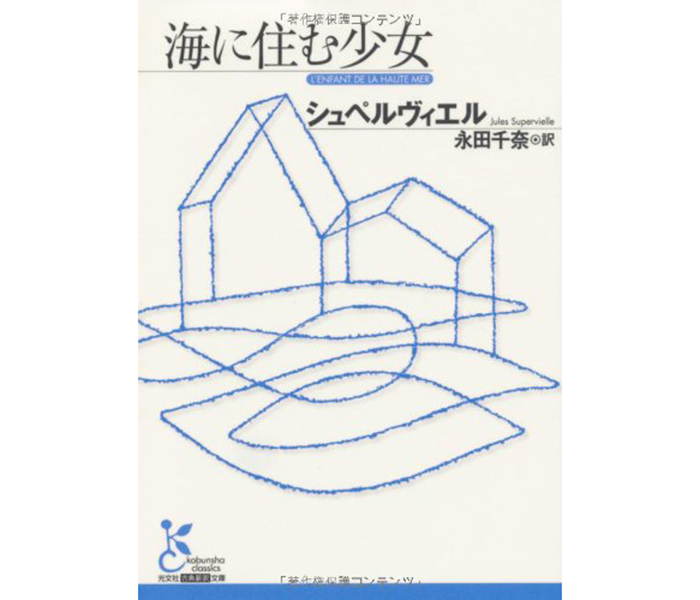2022/03/08
坂上友紀 本は人生のおやつです!! 店主
『海に住む少女』 光文社古典新訳文庫
シュペルヴィエル/著 永田千奈/訳
シュペルヴィエルの名をはじめて知ったのは、堀口大學の訳詩集『月下の一群』を読んだ時でした。次にその名がインプットされたのは、大正・昭和期の日本の詩人や小説家の作品を読むようになったころ。西條八十や堀辰雄といった「好きな作家の、好きな作家」であるところのシュペルヴィエル!
……となると俄然読みたくなったものの、当時は(そして今も大概)絶版かつ入手困難なものが多く、古本屋さんに行った時には必ず探すようにして、ようやく見つけたのが数年のうちでわずかに二冊。基本的に実店舗でしか本を買わないので、「読みたい!」のになかなか読めない作家だったのですが、ありがたいことに2006年に光文社古典新訳文庫から『海に住む少女』が、次いで『ひとさらい』が刊行されて、今に至るのでありました☆(ちなみに『海に住む少女』は素晴らしいことに、現在5刷!)
不惑を過ぎたからなのか、最近はむかし読んで良かった本の再読がマイブームで、この『海に住む少女』もそんなことで久々に紐解いた一冊だったのですが、実によかった。本当によかった。収録されたどの物語も、なんなら二十代の初読時よりもひどく心に響いたのですが、その理由がどこにあるのかといえば、若いころに比べて「喜怒哀楽」の「哀」をいくつか経験したところにあるような気がしています。
シュペルヴィエルは詩人かつ小説家だったウルグアイ生まれのフランス人で、本書には短めの物語が10篇収録されています。訳者による「あとがき」のなかで、『いちど、彼(注:シュペルヴィエル)の作品を読んだことのない人にその魅力を説明しようとして、苦しまぎれに「フランス版宮沢賢治」という言葉を使ったことがある』と記されているのですが、それはたいへん言い得て妙! ただし、同じ訳者による二作目の翻訳作品『ひとさらい』のあとがきにおいては、「フランス版宮沢賢治」という言葉がひとり歩きしすぎたー!的なことも書かれているので、「宮沢賢治」というワードが日本人に及ぼす大きすぎるイメージについては、ちょっぴり考慮せねばなりません。しかし、この言葉(フランス版宮沢賢治)が内包する「詩人が書いた小説」という部分については、強調しすぎる心配なし!
その理由は、例えば以下においても顕著です。
時折、少女はどうしても、何か文章を書かずにいられない気分になります。そして、一生懸命に文字をつづります。
いろんなことを書くのですが、そのなかの一部を見てみましょう。
「これをふたりでわけましょう。どうですか」
「聞いてください。おかけください。動かないでください。おねがいです」
「もしわたしに高山の雪がひとかけらでもあれば、一日があっという間に終わるのに」
「泡よ、泡よ、わたしのまわりの泡よ。もっと硬いものになれないの?」
「輪になるには、最低、三人がひつようだ」
「埃の舞う道路を、顔のない二つの影が逃げ去ってゆきました」
「夜、昼、昼、夜、雲、それから飛び魚たち」
「何か物音が聞こえたように思いましたが、海の音でした」
(『海に住む少女』 「海に住む少女」より)
ベツレヘムへの途上、ヨセフの引くロバの背には、マリアが乗っていました。マリアは重くありませんでした。未来のほかに、何ももっていないからです。
牛はひとり、あとをついてゆきました。
(略)貧しくて、晴れやかな表情を浮かべる以外に、お祝いをもってくることができないひとたちでした。
(略)体じゅうがうれしくて、角の先っぽまでうれしさのかたまりでした。
(『海に住む少女』 「飼葉桶を囲む牛とロバ」より)
枚挙にいとまが無いのでもうやめますが、表題作「海に住む少女」で、とある少女が手慰みに書いた一文一文は、すでにして一つの詩であるかのよう! また、「マリアは重くありませんでした。未来のほかに、何ももっていないからです」の文は、さらりと読ませながらも想像力を刺激してやみません。
ところでこれは「訳しかた」のセンスの話になりますが、「一匹」ではなく「牛はひとり」という日本語の選択も素敵です。ちなみに「飼葉桶を囲む牛とロバ」はイエス生誕の時に馬屋でイエスの両側に侍っていた牛とロバの「牛目線」で語られていく物語なのですが、童話風にひらがなを多用して訳されているのも物語にぴったりしているし、「体じゅうがうれしくて」も「うれしくて」と「嬉しくて」では読者の受け取りかたが大違いで、「うれしさのかたまり」という優しい表現が、主人公である牛のキャラクターにこれまたカチッとはまっているのです! フランス語ができないので残念ながら原文では読めないのですが、きっと原文の味わいを訳者の方がきちんと伝えてくれているのだろうなー、と勝手に思っています。
この二作以外にも、セーヌ河で溺死した十九歳の若い娘(「娘」にかかるこの波瀾万丈な形容詞!)が水底をさすらう冒険譚(「セーヌ河の名なし娘」)だとか、声がヴァイオリンの音色の少女が主人公のお話だとか(「バイオリンの声の少女」)、一風変わった設定が多いのも詩人であることの証左の一つと考えますが、表題作の「海に住む少女」がやはりシュペルヴィエルの真骨頂だと言いたい気持ち。
「海に住む少女」は海のなかにある町にただ一人暮らす十二歳の少女が主人公のお話で、その町は大西洋のまっただなかに浮かんでいながら誰からも見えず、知られないまま存在しています。仮にどこかの船がその町に近づいてくることがあれば、少女はとても眠たくなって、町はまるごと波の下に消えてしまいます。朝になれば焼きたてのパンがパン屋のカウンターに置いてあり、少女が家でジャムを使っても、次の日にはまた未開封の状態に戻っているし、学校も役場もあって、火も使えれば電気だって通っています。ただし、町には少女以外に誰の姿も見当たりません。来る日も来る日もただひとり、眠って起きて、学校に行っては勉強し、時に家のなかで写真を見ては、何だか居たたまれない気持ちになって、写真のなかの少女のほうが、正しいような、本物のような気がしたり……。
そんなある日、まるで運命のいたずらのように、あるいは運命の確固たる意志にほころびが生じたかのように、変化が訪れます。小さな本物の貨物船が町の海の道を通り過ぎて行くのに家並は海中に消えることもなく、少女も睡魔には襲われなかったのです……!
(「海に住む少女」から要約)
で、このあとどうなったかをすべて書くのは野暮なので書きませんが、これこそ「詩人が書いた物語」でしかないです。と言うのも、例えば「かなしみ」を表すのに、「◯◯が死んでかなしい」と書かれていれば、原因と結果が明確なので非常にわかりやすい「かなしい話」なのですが、「海に住む少女」の場合、「かなしい気持ち」を、ひたすら煮詰めて濾過したら、純で透き通ったビー玉のような、かなしい物語になった!みたいな印象を受けます。かなしいけど綺麗。でも、かなしい! そして、こういう表現方法こそまぎれもなく詩に由来すると感じます。宮沢賢治や堀辰雄、西條八十らにも通じる「詩人のスタイル」です。
詩人・シュペルヴィエルの紡ぎ出す物語は、どれもこれも、美しくって、不可思議で、少しかなしい。かなしくってさびしい。だけど、このどうしようもないかなしみやさびしさが、愛する人たちとともに生きてゆく喜びをもまた背中合わせに感じさせてくれるのでした。