2022/09/02
坂上友紀 本は人生のおやつです!! 店主
『増補改訂版 奇妙な孤島の物語 私が行ったことのない、生涯行くこともないだろう55の島』河出書房新社
ユーディット・シャランスキー/著 鈴木仁子/訳
「地図」とは一体、なんなのか。「地を表す図」。とはいえ、地という立体を正しく図という平面にするのは、無理がある。となると「地図」って一体、なんなのか……!
世界をひと目で見わたせるようにしたい–だがそこに生じる問題には、けっして満足のいく答えは出ない。いかなる投影法で描いても、世界は歪んでしまうのだ。距離が合わないか、角度が合わないか、面積が合わないか。たとえば角度が正しく表現される図法で描くと、陸地の大きさはあられもなく歪められる。(略)地球という球面を面積・距離・角度とも同時に正しくひとつの平面に投影することは、端的に言って不可能なのだ。二次元の世界地図は、ひとつの妥協のかたちであり、地図はその妥協によって、思い切って単純化する抽象と審美的な世界の所有との間をなす芸術となったのである。(略)一見客観的なふりをした世界の全体が示されることになった。
(『増補改訂版 奇妙な孤島の物語』 「はじめに」より抜粋)
「地図は地図」だとなんの迷いもなく捉えていたのですが、このユーディット・シャランスキーの言葉を読んだが最後、その考えを改めざるを得なくなりました。
「世界的な共通認識(であると思っていた)地図」を、ここで言うように「思い切って単純化する抽象と審美的な世界の所有との間をなす芸術」と見做すのならば、それはひとりひとりにとって別物であるはずだからです。
以前『魂を撮ろう』(石井妙子著/文藝春秋刊)のレビューのなかで、「魂あるいは心を育み、時に国や時代によって移ろうこともある『善悪』の判断を作るものは何かと言えば、それはきっと『芸術的なもの』によるのではないか」と書いたことがあります。
芸術を芸術たらしめるものは個々人の持つ感受性であり、そして感受性とは自らの経験をして培っていくもの。だとすれば、それは生まれた国や時代によって、そしてまたひとそれぞれの経験が異なる分だけ違うものであって然るべし!
となると「芸術」であるところの「地図」とはやはり、ただの「地を表す図」ではなくて、ひとそれぞれで実は別の見えかたをしているなにか、ということになります。シャランスキーの話は、地理学であると同時に文学の話でもあるのだなぁ!
ごくごく端的に本書を説明すれば、「実際にこの地球上にある55の島の図とその島の歴史とが記されている本」です。「図と歴史とが記されているだけ」にも関わらず、それはノンフィクションというにはあまりに想像力を刺激してやみません。実際のところも「想像」ではなくむしろ「事実」の範疇において島の歴史が綴られていくのですが、読んだ感想としては、虚とも実と言えないなんとも捉えがたい趣きの作品です。
「文学の棚なのか、紀行エッセイの棚なのか、地図の棚なのか、書店が置き場に悩むような本」とは訳者の言で、まさにジャンル分けすること自体がナンセンス!だと感じるぐらいに、複雑に実と虚の襞が重なり合っているような本なのです。加えて装丁も秀逸なため、普段「デザイン」より以上に「言葉」に興味を持つひとにはデザインへの興味が生まれるかもしれないし、逆に「言葉」以上に「デザイン」に興味を持つひとには、「言葉」に対する興味がより生まれてくるかもしれません。
このような現象が起こり得るのは、著者が「作家であり、ブックデザイナーでもある」ところによる部分も大きいです。本書に掲載された55の島については、文章のみならず、掲載された地図もすべて著者自らが手がけています(※)。日本語版では見開きの1ページで1つの島を紹介する仕様となっていて、右ページにはフィクションのようでありながらノンフィクションである島の歴史が、そして左ページにはノンフィクションのようでありながらフィクション(=思い切って単純化する抽象と審美的な世界の所有との間をなす芸術)である島の地図が表されているところも、虚実が入りまじる不思議な雰囲気を醸し出している理由のひとつだと思います。
※原書となるドイツ語版では、文章と地図製作に加えて装幀も自ら手がけている上に、「ドイツのもっとも美しい本」賞を受賞。
著者が自らデザインできるだなんて、なんていう強み!
思考をかたちにできるからこそ、フィクションとノンフィクションを繋げることがうまいのだと感じるし、また日本語版においては、シャランスキーのその強みを余すところなく伝えてくれている訳者の絶妙なるトランスレーションについても触れておかねばなりません!
たとえばシャランスキーが記す「地図上の地名」について。
島の歴史と人の想いを静かに、おのずと語っている地名。それをカタカナと漢字で表してしまうとかえって理解しがたく、多くが失われると思われた。地図の名称を何語だろう、なぜ英語らしいものとスペイン語らしいものが混じっているのだろう、この人名はなに? この名前はあんまりな……などと思いながらじっくり眺めているうちに気づくことや想像(妄想)できることは山ほどあり、読者は各人各様にかならず発見と想像の喜びを味わうことと思う。だからあえて〈日本語による征服〉はしていない。
(『増補改訂版 奇妙な孤島の物語』 「訳者によるあとがき」より抜粋)
……という明確な意図のもと「地図上の地名」は「日本語にしていない」。しないという選択により、この本が日本語の本として「トランスレーション」されているのです。
余談ですが、わざわざ()に入れて「妄想」と書いているところや、ひらがな表記にすることによって力強くもやさしく感じる「かならず」の言葉が、これまた心に響いてくるのです!
そしてさらなる余談ですが、わたしが本書を手にした理由は訳者が他ならぬ鈴木仁子さんだったからで、鈴木さんといえばゼーバルトの翻訳者としても名高いあの鈴木仁子さんです。日本語によって生み出すことができる「光と翳」を完全に制している(ところが、鈴木仁子さんの翻訳文の最大の魅力であると勝手に思っていますー!)、翻訳者さんなのであります! 仮に「かげ」一つとっても、「かげ」、「カゲ」、「影」、「陰」、「翳」……といった数多のバリエーションを持つ日本語で本が読めるとはなんと贅沢なことであるかと、いつも噛み締めさせてくれるかたです。
外国文学が心に響いてくるかどうかは、原書で読めない限りは結局のところ翻訳者さんの言葉づかいと自分との相性による気がします。それと、これは外国文学だけではなくて遍くすべてのジャンルの書物に対して言えることですが、組版も含めた本の装いによると思う!
閑話休題、そんなこんなですみずみにまで気を配られた本書の肝心の島の話について、強烈だったものをいくつか以下に。
サン・ポール島の話
————————–
19世紀、英国の軍艦が航行不能に陥りとある島に乗り上げた。その島には2人しか人間がいない。にも関わらず、ひとりは〈総督〉と名乗り、もうひとりは自分を〈家臣〉だという。〈家臣〉は口を開ければ〈総督〉のことを、〈たいそうな善人〉だと語り、〈総督〉は〈家臣〉のことを〈根っからの悪党〉だとののしった。が、噂によると、かつてこの2人と共に黒人と白人の混血であるムラートが住んでいたが、この〈善人〉と〈悪人〉が共謀してその男を殺し、死体を食べ、そして遺骨を小屋に隠したという。(……えーっ!)
フロレアナ島の話
————————–
最初に2人が、ついで3年後に3人が「国家の支配がおよばず、必要性の法だけに支配される地」に向かった。さらに2年後には5人のうち2人が行方不明、1人が死体となって発見され、その後1人が服毒自殺。残る1人が国家の支配する島の外の世界へと舞い戻ったという。さて、犯人は……?(さらに、えーっ!!)
……その他、島のなかだけで流行る病気、奇習、暴力についてなど、本当に事実なのかと疑いたくなるような話ばかり。ですが、本書の「はじめに」に「小さな大陸はミニチュア版の世界である。(略)ここで起こることは、凝縮されてほぼ必然的に物語となり、どこでもない場所の室内劇になり、文学の素材になる。それらの語りに固有なのは、真実と詩作が分かちがたくなり、現実が虚構となり、虚構が現実となることだ」と書かれていることを鑑みても、事実であること、または虚構であること自体が大事というよりも、むしろ「本当なのかしら」と思わされる行為こそが、まさに人が本を読む理由に直結していくのだと感じます。
著者の生まれ育ち(まだドイツが東西にわかれていた時代の旧東ドイツの出身。1980年生まれ)も本書を読むに際して見過ごせない部分ではありますが、なにをさておいても本を読むとはなんと楽しく、なんと世界を広げてくれることか!と沁みじみ心に思わせてくれる『増補改訂版 奇妙な孤島の物語』なのでありました☆★☆
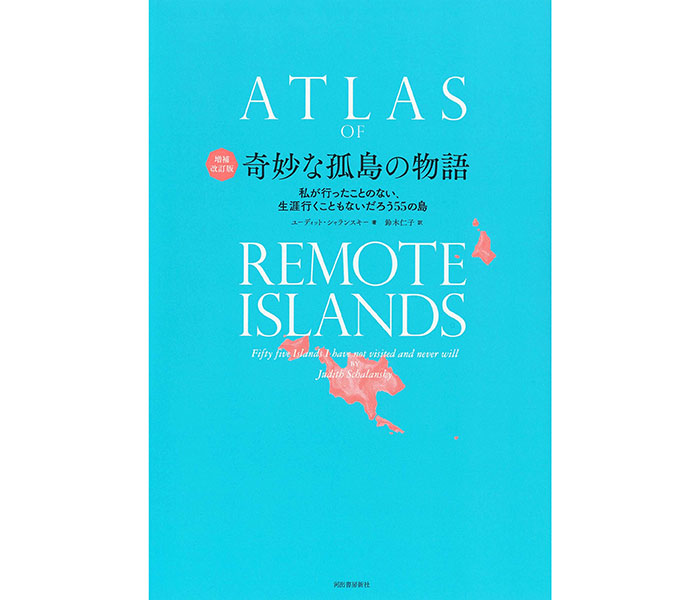
『増補改訂版 奇妙な孤島の物語 私が行ったことのない、生涯行くこともないだろう55の島』河出書房新社
ユーディット・シャランスキー/著 鈴木仁子/訳

