ryomiyagi
2019/11/12
ryomiyagi
2019/11/12

日本シリーズでは「ON対決」以来となった、ホークスとジャイアンツのマッチアップ。この対決では「#お股本」にも詳しいスラッター投手の活躍、フライボール革命によるホームランの応酬など、現代のトレンドを詰め込んだような対決が繰り広げられた。
そういった点はお股ニキ氏に触れてもらうとして、今回私は、シリーズで相対した工藤・原両監督の采配・戦術について語ろうと思う。
横浜ファンながら、巨人とソフトバンクという「球界の盟主対決」とも言えるこの勝負を偉そうに論評することをお許し願いたい。
ソフトバンクの工藤監督はある種の「博打」的な采配を、勇気を持って断行できるタイプの監督だ。
一方、巨人の原監督はCS阪神戦でのダブルスチールなど相手の裏をかくことには長けているが、確率の低い賭けに挑むタイプではない。
競馬っぽく言えば、前者は大穴を買うタイプで後者は賭け方が上手いタイプに例えられる。長い目で見れば後者、すなわち原タイプの方が低リスクで、より高い金額を得られるだろう。
実際のところ、長期戦のペナントレースで巨人は優勝したのに対し、ソフトバンクは2位に終わっている。
しかし、短いスパンで見れば前者は1度当たった時のリターンが遥かに大きい。原監督が長期戦に強い一方、工藤監督は短期決戦に極端な強さを見せるのは、こういった要因があるのだろう。ソフトバンクに関しては、賭けに対して応える選手たちのクオリティも相当に高い。
まずは原監督の采配について、象徴的な場面に触れたい。CSのファイナルステージ第2戦、3点リードで迎えた巨人の5回裏の攻撃。状況は1死1、2塁。打席には3番の丸佳浩。
ここで原監督は2塁走者・亀井と1塁走者・坂本のダブルスチールを敢行し、見事に成功させた。
丸は左打席なので、捕手は3塁へ投げやすい。しかも、その捕手は盗塁阻止能力に長けた梅野である。常識から考えればありえない采配だろう。
しかしこの場面、バッテリーは2年連続MVPである強打者の丸をどう抑えるかに全精力で集中しており、走者を気にしていられる状況ではなかった。当然、ダブルスチールなど全く警戒していなかっただろう。
成功する確率が高いと思えば、常識外れな采配であろうと平気で実行する。それが原辰徳という監督である。相手の想像を超え、惑わせるその一手はまさにマジックのようだ。
一方、工藤監督の采配を象徴するシーンがあったのでこちらもご紹介したい。日本シリーズの初戦、7回裏1死1,3塁で1番の牧原が打席に立った場面だ(投手は左の田口)。
ここで工藤監督は偽装スクイズによる1塁走者・川島の盗塁で2,3塁の状況を作り、牧原の一打に賭けた。結局その通り牧原が2点タイムリーを放ったのだが、この場面を細かく見ていこう。
ソフトバンクはこの時2点リードで、なんとしても次の1点が欲しい場面。というか後ろのリリーフがモイネロと森唯斗であることを考えれば、もう1点あれば十分である。
牧原は対左投手に特段の強みはなく、ひっかけてセカンドゴロを打ってしまうことも多いる。ただし、併殺になることは考えにくい程度の走力を持っている。
そのため、守備側が守りにくい1,3塁のままにしておいて、仮にセカンドゴロを打っても点が入る可能性を残す手もあった。これなら、より高い確率で貴重な追加点がソフトバンクに入る。
だが、工藤監督はシーズンで対左投手の打率が2割を切る牧原のヒットに全てを賭け、成功した。この強気の“ギャンブル“で一気に2点が入り、試合そしてシリーズ全体の流れが完全にソフトバンクへと傾いた。
ソフトバンクが2011年に戦った日本シリーズ(vs 中日)で、無死満塁から登板した森福が3人を打ち取った“森福の11球“という有名な場面がある。
これについて、当時の敵将・落合監督が「その前、無死2、3塁での5番・和田一浩のフォアボールが要らなかった。ひっかけてショートゴロで1点入ればいいと思っていた」と悔やんでいる。
満塁になってからでは攻撃側も作戦の取りようがなく、打順も下がっていく。フォアボールは一見するとチャンス拡大のようだが、チームが勝つために必要な手は案外違ったりするものである。
あと1点で試合が決まる場面で、3塁走者さえ還ればなんでもいい、内野ゴロでいいから打つ。綺麗な点の取り方ではないのだろうが、こういう考え方も引き出しのひとつとして持っておくべきである。短期決戦ならば、なおさら必要となるだろう。
ちなみに工藤采配の象徴として挙げた先の場面では、牧原のタイムリーの後に今宮、柳田の連打で再び1死1、3塁の形ができ、4番・福田秀平のセカンドゴロで更に追加点が入った。この時の福田の働きが、目立たないながらもチームの強さになるのだ。
野球は正解のないスポーツだ。
打撃フォームや投球フォームがそうであるように、戦術も監督によって大きく異なる。こういった違いを存分に感じながら、まだまだ試合を楽しんでいこうではないか。
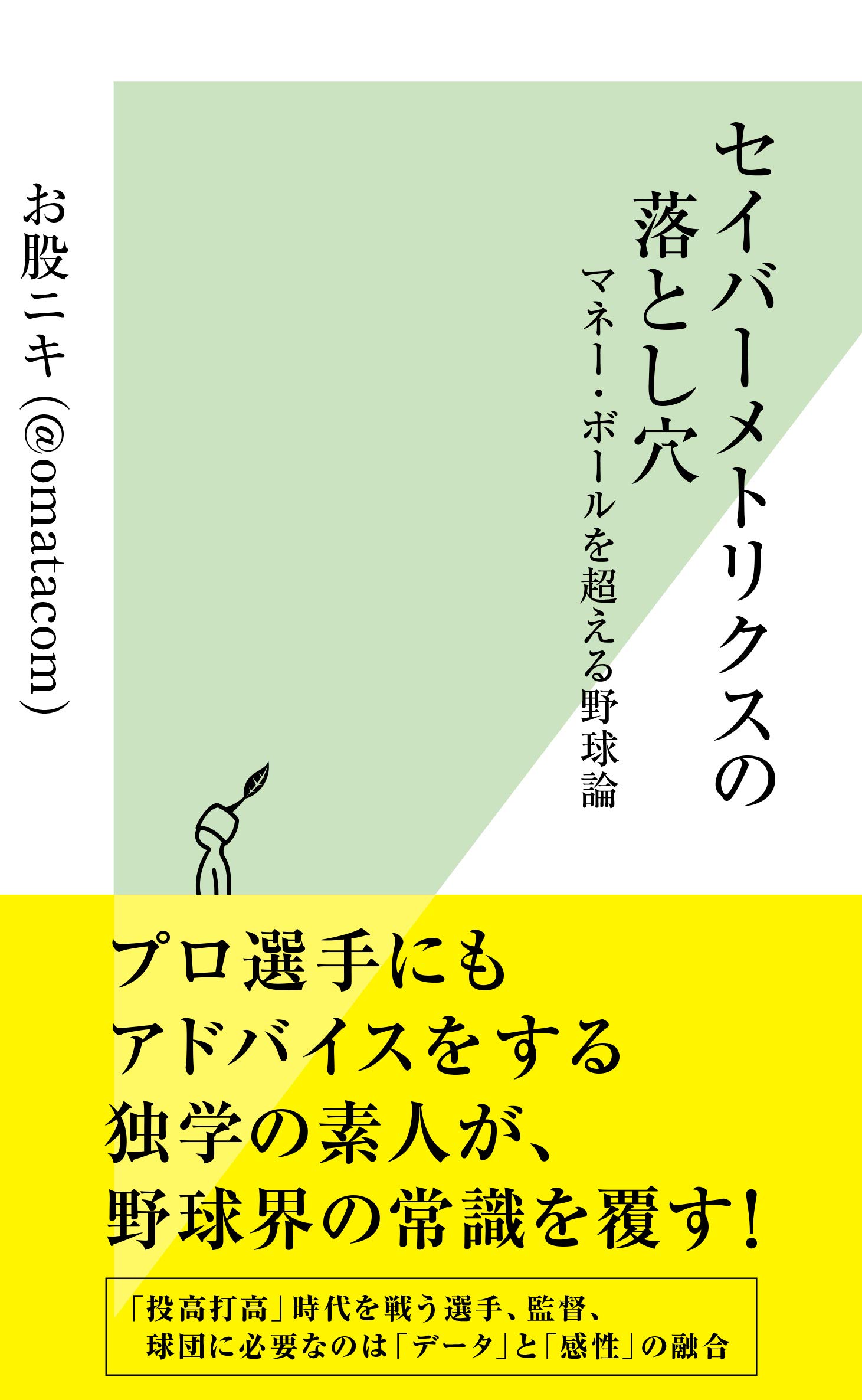
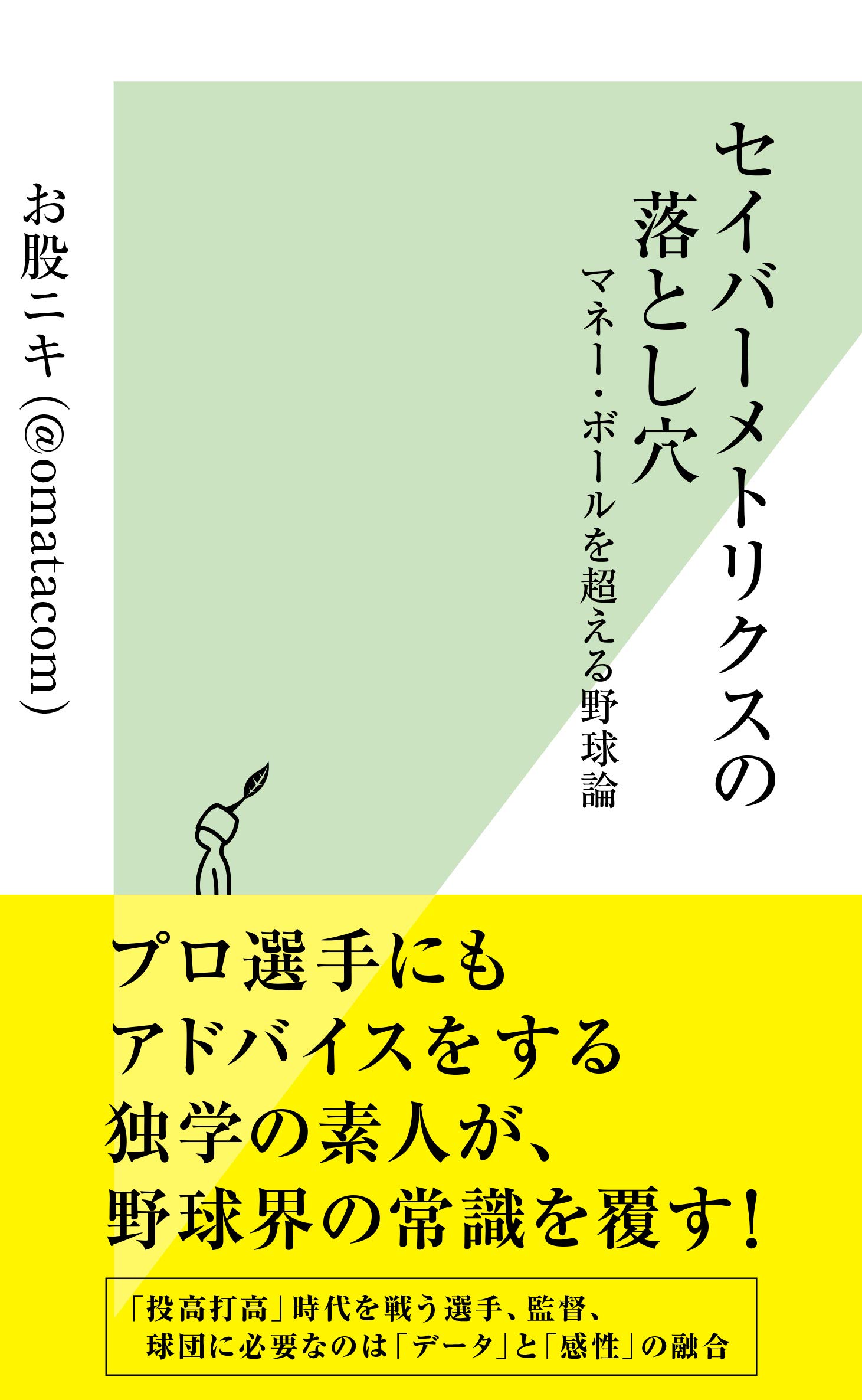
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.