akane
2019/05/15
akane
2019/05/15

辻田真佐憲『大本営発表』(幻冬舎新書)2016年
連載第17回で紹介した『「本当のこと」を伝えない日本の新聞』に続けて読んでいただきたいのが、『大本営発表――改竄・隠蔽・捏造の太平洋戦争』である。本書をご覧になれば、そもそも「大本営発表」とは何だったのか、それがなぜ「権力者に都合のよいデタラメな報道」を意味するようになったのか、そこから何を学ぶことができるのか、明らかになってくるだろう。
著者の辻田真佐憲氏は、1984年生まれ。慶応義塾大学文学部卒業後、同大学大学院文学研究科中退。現在は文筆家。専門は近現代史。とくに戦争と社会・文化との関連についての研究で知られ、『愛国とレコード』(えにし書房)や『日本の軍歌』(幻冬舎新書)などの著書がある。
連載第16回と第17回では、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」に触れてきた。東京電力福島第一原子力発電所事故は、それまでに電力各社が巨額の広告費を費やして新聞・雑誌やテレビ等のメディアに宣伝してきた原子力の「安全神話」を完全に崩壊させた。
「国際原子力機関(IAEA)」が定める「国際原子力事象評価尺度(INES)」(レベル1=「運転制限範囲から逸脱」~レベル7=「深刻な事故」)に対して、日本政府は、事故直後に「レベル3」(重大な異常事象)、翌12日には「レベル4」(発電所外に大きな危険性を伴わない事故)と認定した。しかし、この見解は「楽観的すぎる」と世界各国の原子力研究機関から批判を浴びた。
欧米のメディアは、3月15日の段階で「レベル6~レベル7」と報道していたが、日本政府は3月18日になって「レベル5」に認定。その後、日本政府、原子力安全・保安院、東京電力が「想定外」を言い訳に迷走した姿を記憶する読者も多いことだろう。事故から1か月後の4月12日、ようやく日本政府は、福島第一原発事故をチェルノブイリ級の「レベル7」に認定した。
さて、前置きが長くなったが、辻田氏によれば、実は2011年には「大本営発表」に関する記事や文献が急増し、国立国会図書館のウェブサイトでは「大本営発表」というキーワードが戦後最大のヒット数を記録した。多くの国民が、原発報道から「大本営発表」を連想したのである!
「大本営発表」といえば、1941年12月8日の「帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり」の開戦宣言が有名で、小林秀雄はこれを「一種の名文」と称した。ところが、当初は冷静に事実を伝えていた発表が、ミッドウェー海戦敗退以降は「改竄」を加えるようになり、ついには完全な「捏造」を発表するようになったのである。
玉音放送前日の1945年8月14日の「大本営発表」は「我航空部隊は、8月13日午後鹿島灘東方25浬に於て航空母艦4隻を基幹とする敵機動部隊の一群を捕捉攻撃し、航空母艦及巡洋艦各一隻を大破炎上せしめたり」と、もはや誰も信じない「お花畑」のような妄想を語っている。
なぜこんなことになったのか。大本営の陸軍部と海軍部の競合や、大本営と協力しなければ情報を貰えない一方、刺激的な記事を掲載して部数を増やしたい新聞・雑誌の暴走など、その原因は本書に詳しく分析されている。しかし、おそらく何よりも根本的に重要なのは、この連載でも何度か指摘してきたように、「見たいものを見る」という人間心理ではないだろうか。
1944年10月14日、鹿児島県鹿屋飛行場に降りた情報参謀の堀栄三少佐は、驚くべき光景を目にしている(『大本営参謀の情報戦記』文春文庫)。戻ってきた海軍航空兵たちが、次々と戦果を報告し、それらが黒板に書き込まれる。「空母アリゾナ型撃沈!」「よーし、ご苦労だった!」「エンタープライズ轟沈!」「やった!」そのたびに「わっ」という歓声が湧き上がる。
堀少佐が、報告を終えた航空兵を呼び止めて、「どうしてアリゾナとわかったか」「アリゾナはどんな艦型か」「暗い夜の海上で、なぜ自分の爆弾でやったと確信できるか」などと矢継ぎ早に質問すると、答えはどんどんアヤフヤになった。航空兵は「見たいものを見た」のである。
「大本営発表」によれば、日本軍は連合軍の戦艦43隻、空母84隻を沈めたことになっているが、実際には戦艦4隻、空母11隻にすぎない。逆に日本は、戦艦8隻、空母19隻を失った。
現在の日本には戦前のような陸海軍もなければ、抑圧的な言論統制の仕組みもない。反対に、表現の自由を保障する憲法や、多種多様なメディアも存在している。ただ、それにもかかわらず、原発の「安全神話」なるものが日本社会を覆ってしまった。われわれが大本営発表の歴史から学ぶべきことは決して少なくないのではないか。(PP. 6-7)
どこから「大本営発表」が生じたのかを歴史的に理解し、想像を絶する「デタラメ報道」を二度と許さないためにも、『大本営発表』は必読である!
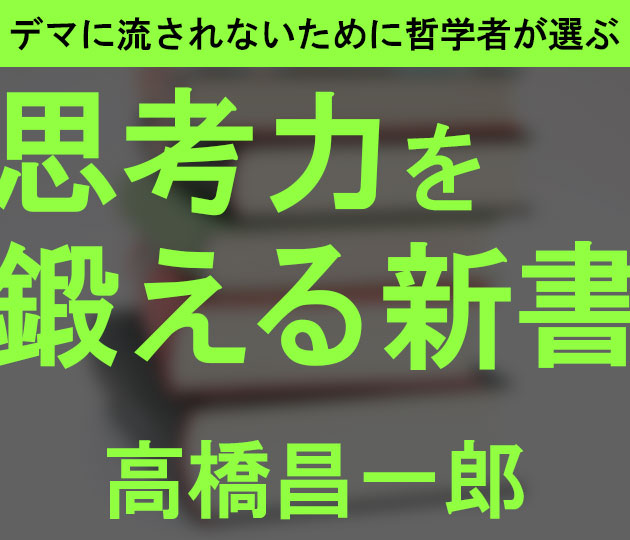
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.