2020/02/10
金杉由美 図書室司書
『ノラや』中央公論新社
内田百閒/著

内田百閒は天下無双の偏屈ジジイである。
坊ちゃん育ちで、わがままし放題で、道楽者で、癇が強くて、いやしんぼで、好き嫌いが激しくて、およそ我慢というものを知らない。
貧乏は平和なんだと言いながら借りた金で贅沢して、自分の収入は月給と借金で成立してるなんて平気でうそぶく。
借金を重ねるだけ重ねた挙句に仕事も家族も放り出して自分だけ逃げだしてしゃあしゃあと別の女性と暮らし始める。
好きな饅頭をしまいこんでチビチビ食べてるうちにカビが生えて嘆いたりする。バナナが食べたいと思ったら頭の中からバナナが離れない。
人と会うのが面倒くさくて玄関に「面会謝絶」と貼り紙してトイレの汲み取り業者に文句言われたりする。
かなり厄介なジジイである。
そんなジジイが飼ってる猫がいなくなったからといって西へ東へオロオロし、帰ってこないと言ってメソメソし、周囲を巻き込んで大騒ぎして探しまくっても見つからなくて号泣し…という顛末を描いたものが本書『ノラや』だ。
もともと猫が好きだったわけではない。
小鳥をたくさん飼っていたから猫は天敵くらいに考えていた。
たまたま迷いこんできたから世話するようになっただけなのに、その猫がいなくなっただけで、あんなにムスッとしたクソジジイが身も世もないほど嘆きまくる。
実は、百閒という人はよく泣いた。
師匠である夏目漱石が亡くなったときは、葬儀場の隅っこで空を仰いでわんわん泣いた。
大好きだった東京駅が空襲で焼けたときは、設計者辰野金吾の息子の家まで遠路はるばる歩いて行って玄関でわんわん泣いた。
親友の芥川龍之介や宮城道雄に死なれたときもわんわん泣いた。
いい年をした大の男が子供のように手放しでわんわんと泣いた。
我慢を知らない百閒先生は泣くことだって我慢しないのである。
夜空の月を取ってくれろと駄々をこねる子のように、地団駄踏んで涙を流すのである。
自分をおいて去っていってしまうものたちへの追慕と憤懣に心の底から慟哭するのである。
永遠に続くものなんてないのは知っているけれど、承知できないのである。
嫌なものは嫌なのである。
ふるさとの岡山にだって、変わってしまったのを見たくなくて帰らなかった。
汽車で通るたびにホームに降りて懐かしいその風に触れ、名物の饅頭を夢にまでみたけれど、それでも一度も帰らなかった。
百閒先生の中には永遠のこどもがいる。
坊ちゃん育ちで、わがままし放題で、遊び好きで、癇が強くて、いやしんぼで、好き嫌いが激しくて、およそ我慢というものを知らないこどもがいる。
無垢で傷つきやすくて愛情にあふれたこどもがいる。
そのこどもが、胸が張り裂けんばかりに泣きじゃくっている。
行かないで行かないで行かないで、と泣き叫んでいる。
だから猫だって、いなくなってはならないのだ。
愛するものはそこにずっといてくれなきゃ困るのである。
それなのにどうしてみんな消えていってしまうのか。
庭の草の向こうに消えていったノラの後ろ姿が忘れられない。
風呂のふたの上に寝ていた様子が思い出されてならない。
ノラ、ノラ、ノラや。
結局ノラは帰ってこなかった。
偏屈ジジイはいつまでもいつまでも、最後がやってくるまで待っていて、それから愛するものたちの後を追ってゆっくりと自分も去っていった。
こちらもおすすめ。
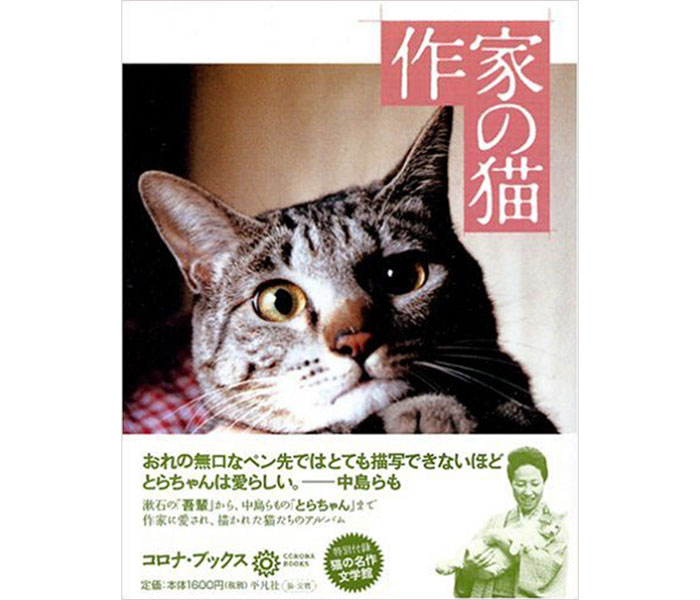
『作家の猫』平凡社
夏目房之介など/著
作家と飼い猫のエピソードが写真とともに詰まっている本。
夏目漱石、中島らも、青木玉など。もちろん内田百閒も。
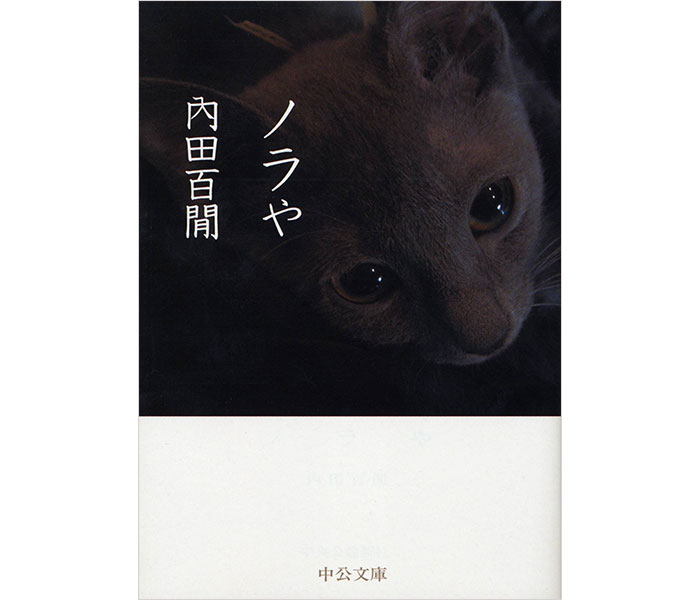
『ノラや』中央公論新社
内田百閒/著

