2022/01/21
長江貴士 元書店員
『ガロア 天才数学者の生涯』KADOKAWA
加藤文元/著
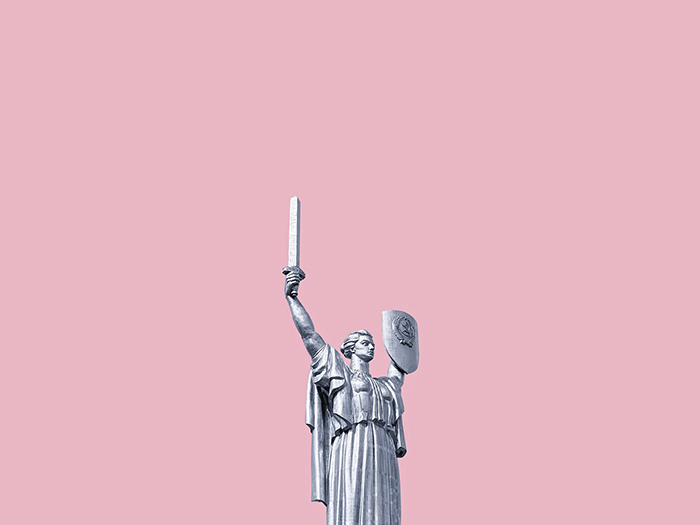
本書は、ガロアという数学者についての本だが、彼の業績を詳しく説明するものではない。ガロアは、現代数学においてなくてはならない存在となった「群論」という分野をたった一人で切り開いた、広く数学の世界を見渡してみてもそうそう匹敵する存在を思いつけないほどの天才だが、本書には「群論」に関する説明はほとんどない。
ガロアについては、「群論」以外にも広く知られていることがある。それは、「20歳で決闘で死んだ」というものだ。そして本書は、彼のたった20年間の生涯において、どのように数学に関心を持ち、どのように「群論」(当然、当時はそう呼ばれてはいなかったが)という発想にたどり着き、そしてどういう時代背景の元で「決闘」が行われるに至ったのかという、数学者ガロアの生涯に焦点が当たっている。
とはいえまずは、群論という理論や群論を生み出したガロアが、数学界においてどう凄いのかということを書いていこうと思う。
本書の著者はガロアについてこう表現している。
現在の我々の状況に翻訳すれば、高校生が突如として現代数学において大発見をする、という感じになるでしょう。しかも、それは単なる発見ではなく、その後の歴史の数世紀分を変えてしまうような種類の巨大で深遠な金字塔なのです。そんなことが本当に可能なのか?と疑いたくなってしまうくらいです
また、ガロアの業績についてはこう評している。
彼は近代数学史上最大の発見と言っても過言ではない、巨大な業績を残しました。ただ単に何らかの問題を解いた、というだけにとどまりません。その業績は、それ以後の数学の歴史を根本から変えたのです。パラダイムを変えた、と言ってもいいでしょう。彼のもたらした原理や考え方は、現在でも数学研究の基層に生きていますし、数世紀先の未来でも同様でしょう
相当の大絶賛だと言っていいだろう。まあその通り。僕自身が実感できているわけではないが、「群論」が無ければ今の数学研究は成り立たないと言っていいでしょう。それぐらい、彼が生み出した「群」や「集合」という概念は、現代では当たり前すぎるぐらい当たり前に使われる武器なのだ。
さらに興味深いことに、現役の数学者でもある著者は、「群論」についてこんな風にも書いている。
もちろん、例えば筆者が1831年当時にこの論文を見ていたとして、これを理解できたとはちょっと思えない。
著者はどうしてこんなことを言うのか。それは、ガロアが「群論」を生み出した当時には、「群」や「集合」という言葉も、「群」や「集合」を使った数学も、当然ならが存在していなかったからだ。例えばこれは、「ストレート」や「キャッチャー」という言葉が存在しないまま野球について説明するようなものだろう。
もう少し別の言い方をしてみよう。よく言われることだが、かつて描かれたSF作品には、「携帯電話」的なものは描かれていない(テレビ電話やトランシーバーは登場するが、誰もが携帯型の端末を持って連絡を取り合うような描写はほとんどない)。つまりそれは、昔の人の頭の中には、「誰もが小型端末を持ってやり取りをする未来」など存在していなかった、ということだろう。
そしてガロアが行ったことは、誰もそんなことを考えていなかった時代に、「色んな人が一人一台端末を持って、自由に通話が出来、世界中の情報にアクセス出来、世界中の人と知り合いになれる、なんて未来が来たら世の中はどうなるだろうか」と想像していたようなものだ。
そんな奴がいたら、「頭がおかしい」と思われて終わりだろう。そう、非常に残念ながらガロアは、数世紀先を行き過ぎていたために、生前(と言ってもたった20年だが)にはほとんど評価されなかった。
しかしごく僅かだが、評価してくれる人もいた。それが、リシャール先生である。先生はガロアの群論に関する論文に感銘を受け、その論文を当代随一の数学者と認められていたコーシーに渡すことに成功する。
さて、ガロアについて書かれた本では、このコーシーは悪者として描かれることが多い。何故なら、このガロアの論文を粗雑に扱ったとされているからだ。実際、この時のガロアの論文は紛失しており、それはコーシーのせいだとされている。また、コーシーはこの論文の重要性を理解しなかったとする記述も多い。しかし著者は、その認識は誤りで、様々な文書や発言から、コーシーがこの論文の重要性を理解していたことが読み取れるのだと主張する。
さらに、数学者らしい指摘もしている。一般的には、コーシーは後年、ガロアの論文に関心を失ったように見えると指摘されており、そのこともコーシーの悪評に拍車を掛けることになっている。しかし著者は、コーシーは「ガロアの論文を理解してしまった」だけではないかと指摘する。恐らく、著者自身の経験でもあるのだろう、研究対象は常に山程存在するから、かつて一度理解してしまった論文への関心が薄れてしまうのは仕方ない、と。なるほど、そう捉えれば、コーシーへの悪評はちょっと可哀想にも思う。
論文の紛失だけではなく、ガロアは色々と不運に見舞われる。その最大のものが、当時の一流数学者たちの<住処>だった「エコール・ポリテクニーク(高等理工科学校)」への入学試験だ。一度目は、あまりにもそこに行きたいという気持ちが強すぎ、一年早く試験を受けたために失敗してしまったが(しかし、そのせいでリシャール先生と出会えたので、悪いことばかりでもない)、二度目はそうではない。学生の身分でありながら既に論文を発表し、紛失されてしまったもののアカデミーにも論文提出をしているガロアが不合格とされてしまう。この結果は、「フランス教育史上でも稀有の大スキャンダルとされた」と本書でも書かれているように、納得感をもたらすものではなかったようだ。
「エコール・ポリテクニーク」への受験は、二度までしか出来ないと決まっていた。そのためガロアは、別の学校に通うことになるが、その学校長の対応や、革命に湧く当時のフランスの時代背景などが積み重なり、ガロアは逮捕や裁判、収容所への収監などを経験することになる。そして「決闘」が起こり、命を落としてしまうのだ。
ガロアの革命的な業績が失われずに済んだのは、友人のシュヴァリエのお陰だ。死を覚悟したガロアは、それまでの業績を大急ぎにまとめ、シュヴァリエに託した。彼がガロアの死後、その業績を広める役を担ったからこそ、こうして僕らは、ガロアの功績を知ることができている。
ガロアという天才数学者の生涯を通じて、当時のパリの雰囲気を色濃く鮮やかに描き出す作品だ。
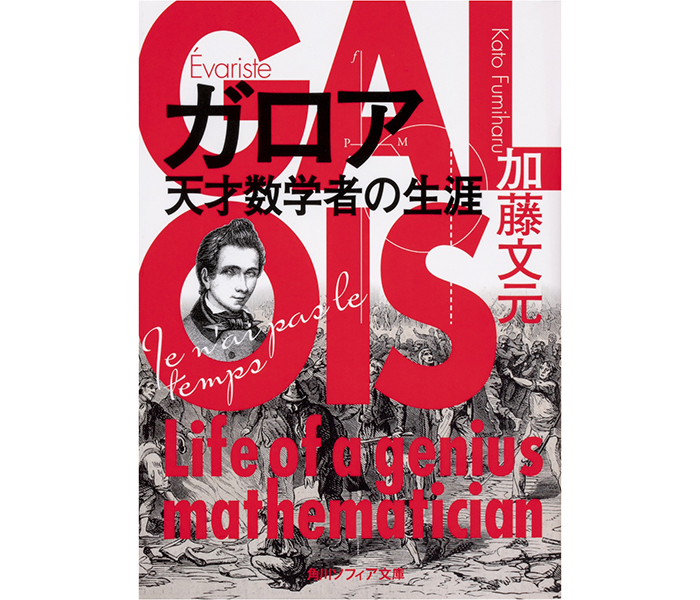
『ガロア 天才数学者の生涯』KADOKAWA
加藤文元/著

