2022/04/08
馬場紀衣 文筆家・ライター
『においが心を動かす ヒトは嗅覚の動物である』
A・S・バーウィッチ/著 大田直子/訳

「におい知覚は私たちに、多くの興味深い知覚体験を突きつける」と語るのは、神経科学や感覚論における「嗅覚」の位置づけを研究しているA・S・バーウィッチ。認知科学者で、哲学者でもある著者はさらにこう続ける。
「たとえば、私たちは風味の知覚が鼻で起こっていることを知っているが、その場所を口の中だと感じる。さらに、あなたも『鼻先』現象に遭遇したことがあるかもしれない。においを認識していて、たとえそれがなじみのあるものでも、その名前を言ったり、表現したりできないことだ。おまけに、におい知覚は、言葉やクロスモーダル(複数の感覚の相互作用)を手がかりに、容易に操られることも知られている。ワインの専門家がバニラの香りと明言すると、それをあなたは感じていなかったが、言われてはじめて知覚しているように思える。」
なんだか自分の鼻が頼りなく思えてくる。たとえば、視覚における色や聴覚における音の知覚は、根本的な原因パラメーター、すなわち光の電磁スペクトルの波長などにもとづいて神経相関へとマッピングされる。だが、「におい」はもっと複雑だ。「におい」の質は、数千個の分子構造をもつ構造的に多様な化学物質によって生まれるが、じつは脳がどのようにして香りを理解しているのかは、あまりよく分かっていない。
しかし、人間は数十万種ものにおいを見事に識別することができる。私たちの生活はにおいに溢れている。ラベンダーの香りに癒されたり、チーズの香りに顔をしかめたり、地下鉄で、美容室で、レストランで、においのせいで不機嫌になったり、気分を高めたりする。日々の生活は、においに支配されているといってもいい。それでいて、においとは何であり、人間の脳がどのようにしてそれを作り出し、意味を与えるのかいまだに理解されていないというのだから驚きだ。
においの科学史は、1991年にリンダ・バックとリチャード・アクセルが嗅覚受容体遺伝子を発見したことで飛躍的に前進した。それまでは、嗅覚はあまり魅力的な研究領域ではなかったようだ。それでも、鼻をめぐる長い歴史には、好奇心と情熱をもって研究に取り組んできたおおくの科学者たちがいる。プラトンは、においは細かい粒子の物理的運動から生じると考えた。においや風味の知覚には、認知の層があるとするアリストテレスの論は、いまだに注目すべき考えのひとつだ。
生理学者エドゥアルド・パウルゼンが1882年に試みた実験は、独創的で、陰惨だ。死体の頭を手に入れたパウルゼンは、まず、これを半分に切った。そして鼻腔に小さな細長いリトマス試験紙をたっぷりと詰めると、人工呼吸装置を挿入し、半分ずつの頭をふたたび合体させた。金属管を気管に見立て、豚の膀胱を肺の代わりにした「模造の呼吸系」が完成すると、パウルゼンは空中にアンモニアをまき散らしながら、その空気を例の鼻へと吸い上げた。いささか乱暴な実験だが、鼻腔内の空気の流れを確認することには成功したようだ。その後、オランダの生理学者ヘンドリク・ツワーデマーカーが馬の死体の頭を複製したもので同じ研究を行っている。発想はよかったが、二人とも「においとは何か」を解明するには至らなかった。
本書では、嗅覚という驚異の感覚世界を幅広い分野を横断しながら解説していく。しかし、最後のページをめくっても、においについての謎は残されたままだ。この20年のあいだに、これまでの数百年をあわせたよりも多くの嗅覚経路が解明された。においについての研究はまだまだ序盤で、ようやく鼻に注目が集まりだしたばかりなのである。
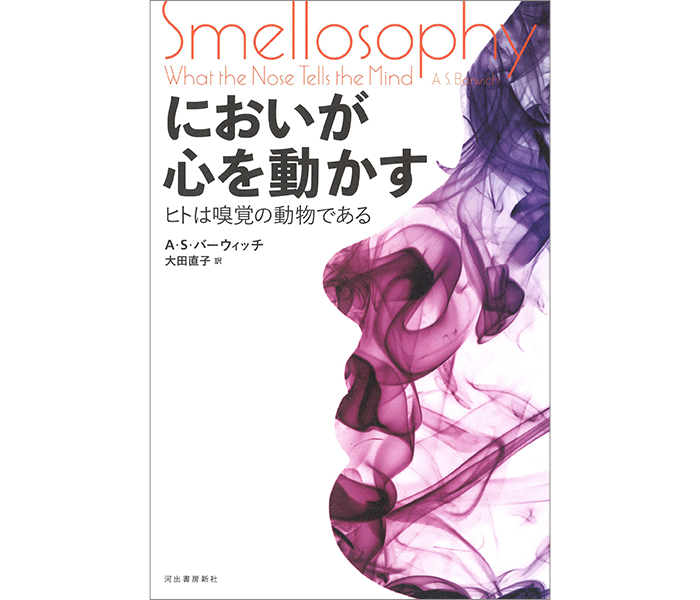
『においが心を動かす ヒトは嗅覚の動物である』
A・S・バーウィッチ/著 大田直子/訳

