2022/11/03
横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店
『掌に眠る舞台』集英社
小川洋子/著
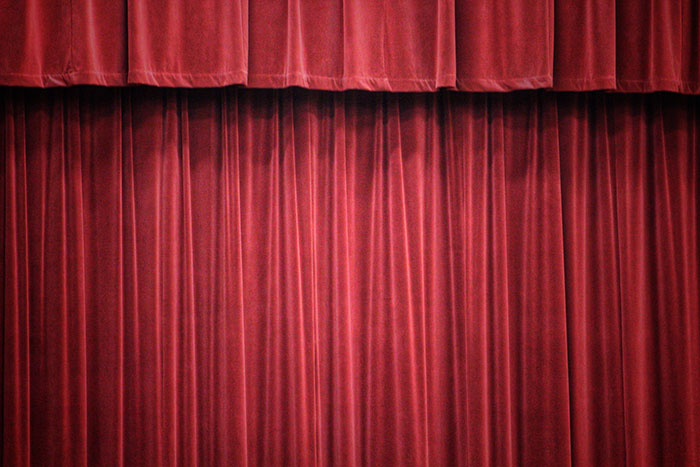
舞台の上で舞い踊る者よ。
無数の瞳に晒されながら、眩い光を浴びていっそう輝く者たちよ。
退屈な日常などこの場所で囁くには相応しくない。
息つく間もないほどのめりこみ夢の世界に芯まで浸るそのひと時に、現実は煙となって立ち消える。
無防備にさらけ出し、浸透するほどに蠢く心。
目の前で繰り広げられる躍動と繋がることだけ願い、ひそやかにはじまった共振を止めることはもうできない。
まるで羽化の最中のような柔く脆い羽に触れることは何人たりとも許されない。
これは、空想の域を超えない語り。
その生まれ変わりの過程を檀上からも見つめている者がいたとしたら。
息を潜めながらこちらの変容をつぶさに見つめる一対の瞳があったとしたら。
互いのまなざしが交差する刹那、異界への扉はぎぎぎと開くだろう。
何を舞うかは知らずともあがってしまった檀上で演じ抜かねばならない。
あの世とこの世の狭間で、幕が閉じられるその瞬間まで踊り続けねばならない。
お城の近くにある文化会館へ縫子さんは少女とバレエの観劇に行く。
演目は『ラ・シルフィード』。
主人公の妖精は透き通った羽をもち、優雅に舞い心のままに踊る。しかし、妖精に心奪われた青年は醜い魔法使いにそそのかされ、美しき妖精を死なせてしまう――
保護者という立場もあって事前に知識を得ていた縫子さんだが、図らずしも公演中に睡魔に襲われてしまう。瞳をらんらんと輝かせながら身を乗り出すほどに夢中になっていたのは少女の方だった。
少女は夢心地のまま、たどたどしい字で「ラ・シルフィード」に手紙をしたためる。
あなたの美しさがどれほどのものであるか。あなたの存在がどれほどの神秘に満ちたものであるか。あなたが、どれほど「わたし」の心に棲みついているか――
少女はしらなかった。
彼女が書き留めた住所はパンフレットを作製した印刷会社のものであることを。
けれど、その間違いを指摘し送り先を正したにも関わらず、返信のない現実が訪れたとしたら、彼女は嘆き悲しむだろう。
縫子さんは少女のために繕ったうす汚れた上履き袋を、妖精からの秘密の手紙を受け取るポストに仕立て上げた。
妖精は透明な羽に模様をつけてほしくて赤ちゃんの周りを舞うのです。
いつか空に向かって手を伸ばしていたあなたの小さな指紋も、妖精の羽を彩る刻印になったでしょう。
ラ・シルフィードとして縫子さんが少女に宛てた手紙から、真実の鱗粉が零れ落ちる。
帝国劇場での『レ・ミゼラブル』全公演七十九公演、S席のチケットを購入したのは、交通事故に見舞われた際の保険金が寸分の違いもなくこれと同じ金額だったからだ。
さらには無料法律相談を受けた帰り、
劇場から出てきた人々の隠しきれない高揚と軽やかな足取り。 力強さが宿った瞳に、
啓示と呼ぶしかない運命の渦中に飛び込んだのは、自らの意思だけではなかったかもしれない。
開幕から十三日目の昼の部、十八公演の幕間。
確信に満ちた感触で彼女の肩を叩いたのは、見覚えのない女性だった。
「毎日、来ている人ですね」
唐突に尋ねられたことに驚きあいまいに首を横に振りながらも、彼女から目を逸らせなかったのは、かつて自分の店で取り扱っていたものと全く同じセーターを身に纏っていたからだった。
「あなたも、よくいらっしゃるの?」
「いらっしゃるも何もないの。ここに住んでいるんだから」
そして二十六公演目、再び姿を現した彼女に誘われるように、いくつもの通路を抜けた先に並んだ小部屋の一番奥の扉の中へと足を踏み入れた。
彼女を劇場で見かけたことは一度もない。
どこで「私」を見つけ、どこから「私」を見つめているのかはついぞ分からぬまま。
彼女が語る「仕事」とは、行き過ぎた妄想の産物か。
彼女の気配のなさは死の世界の住人であるということの表れか。
秘められ閉ざされた部屋の中だけに彼女の香りが濃密に立ち込める
黄泉の世界の扉はあちら側からしか開けられず、その時は永くは続かない。
だとしても、彼女と過ごした時間がすべて幻であったとも信じられない。
虚構は「あちら」であると、立証できる術を私たちは何ひとつ持ち合わせていないのだから。
彼女は十九歳の時からコンパニオンとして働いてきた。
最初の雇い主はお金持ちの未亡人で、
旅先で年の離れた二人は祖母と孫に間違われ、また各々がその役を演じていたともいえる。
未亡人のとめどないお喋りに、穏やかな微笑を添えながら肯定の意を込めた相槌を打つ。
これこそが、コンパニオンとしての雇われた意味そのものだと知った。
一つの契約が終わればまた新たな話が舞い込み、「私」は様々な雇い主の元で数々のドラマを見守ってきた。
そんな中でもとりわけ―――語らざるを得ない雇い主の存在があった。
N老人は七十代後半の長身、スマートな佇まいの男性で今まで従事したどの雇い主よりも立派な屋敷に住んでいた。
依頼内容は、お屋敷に住み込むこと、いつ仕事の要請があっても応えられるよう部屋で待機しておくといういささか変わったものだった。
初めて老人に会った時、その印象的な眼球に視線が吸い込まれるようだった。
眼球と呼ぶにふさわしいそれは、まぶたを大きく押し広げ、濡れた表面がせり出しているようにさえ見えた。
採用が決まり安堵したのも束の間、老人の案内された仕事場兼住居になる部屋はどう見ても小さな劇場だった。
N老人は自分だけのための劇場を欲し、そこには装飾用の役者が必要だった。
鐘撞堂や孤児院、水車小屋やあまつさえ墓地まであり、「私」に用意されたのは見せかけの窓や安物の小物が並ぶ、女性用の部屋という名の舞台だった。
舞台に存在すること。
それだけが重要な役目である日々は全く退屈で、同時に神経をすり減らすものでもあった。
用意された舞台衣装も、見栄えのためだけにする派手なメーキャップにも到底馴染めず、誰もいない観客は闇の塊であり、墓石のように死者の気配を漂わせる。
外の世界から隔離され、ただ舞台に必要な要素だけが閉じ込められたこの場所は、人工的な一個の惑星のようだった。
N老人はいつも突然姿を現した。時間だけは決まっていて、十三時か十九時、昼公演か夜公演を想起させるいずれかだったが、杖の音がするまでその来訪を知ることはできない。
B列6番。老人がいつもの席に座ると、装飾用の役者として立ち振る舞う「舞台」が彼だけ
のために幕を上げた。
演技中、
眼球の粘膜に搦め捕られ、瞳の中心に吸い寄せられ、やがて水晶体に閉じ込められてゆきます。
濡れながら鈍い光を放つ眼球に晒され取り込まれ、もうどこにも逃げられはしない。
ただ視線を受け止めるだけの日々は唐突に終わりを告げた。
しかし、あの眼球によって語らされる物語が消えることはないのだろう。
闇夜に浮かぶてらてらとした粘膜は今なお彼女を見つめている。
八編の掌編が収められた物語について、私が語れることは多くはない。
黄泉の世界の入り口で手招きをする使者に導かれるよう引き込まれたのは、蠱惑的で危険をも伴う舞台だ。
虜になるほど影は薄まり、同時に鼓動がいつもの旋律から逸脱していく。
引き換え、代償。
こんな言葉が浮かびながらも引き戻せなくなってしまったのは、神なるものに動かされてのことであればとひたすらに願う。
だからと言って止めることはしない。
いっそのこと、こちらへと進んできてほしいと思ってさえいる。
“あなた”にとって物語はどんな作用をもたらすだろう。
白日のもとに晒されたのは、どんな姿かたちであるだろう。
陰も光も受け止める。だから。
扉の前で落ち合いましょう。
いつか、舞台の上で抱き合いましょう。

『掌に眠る舞台』集英社
小川洋子/著

