ryomiyagi
2020/10/22
ryomiyagi
2020/10/22

2019年11月22日に中国の湖北省武漢市で原因不明のウイルス性肺炎の症例が確認されて以降、またたく間に世界中へと拡大していった新型コロナウイルス感染症。フランスのマクロン大統領は「我々は(ウイルスとの)戦争状態にある」と宣言し、環境哲学者ティモシー・モートンはコロナウイルスを「友であるかもしれないし、殺人鬼であるかもしれない両義的な存在」と考え、ウイルスとの共生を唱えた。
いくつかの季節がめぐった今も日々カウントされる感染者数は、地球がどこまでも地続きであり、人類がみなひとつの場所に住んでいることをいやおうなしに自覚させる。私もまた、これほどまでに隣人の存在を強く意識したことはなかった。
「人類がラスコー洞窟の壁面に、生命賛歌あるいは人知を超えた何ものかに対する祈りを描いて以来、アートは人類の叡智を結晶化した文化遺産として常に珍重され貴ばれてきました」と語る著者は、本書で人類がどのように疫病と対峙し、アートで表現してきたかを振りかえっている。
たとえば人気の絵本・アニメ『アンパンマン』に登場する敵役でおなじみの「ばいきんまん」は、ご存知の通り、不潔好きで掃除嫌いの、黴菌を擬人化したユニークなキャラクターだ。原作者のやなせたかしさんは、第二次世界大戦での従軍経験から「戦いにより、破壊あるいは汚染された自然や建造物に対する後始末や謝罪」を重視したヒーロー像を生みだした。
ウイルスの感染拡大は経済活動を休止、あるいは停止させ、甚大な損害を与え続けている。人々の活動範囲は狭まり、窮屈な暮らしに辟易している人たちの存在が目立つ一方、数十億人をステイホームさせた結果として、皮肉なことに世界各地の大気汚染レベルは(一時的ではあるが)急激に低下した。
空だけでなく、海も深刻な問題を抱えている。食の多様化、深刻な海洋汚染や温暖化のために、マグロやイルカ、クジラと言った大型の海洋生物が絶滅の危機に瀕している。
長谷川愛の《私はイルカを産みたい…》(2011~13年)は、「子どもを産むという自然の欲求と人口増加抑制の両立に加え、食糧問題の解決や貴重な海洋生物の保護」を目的に制作された作品だ。産むことと食べること、どちらも人間的な、ポスト人間中心主義時代を象徴する作品として挙げられている。コロナ感染拡大の影響をうけて開催が遅れた「オラファー・エリアソンときに川は橋となる」も「地球への生成変化」を問う内容となっている。
気付かずに、いやどこかで微かに気づいてはいるのだけど、まあ、いまのところはこれでいいだろうと、その日暮らしをしているうちに差し迫ったものになっている。コロナによってもたらされた新しい生活は、私たちの意識だけでなくアートにも影響を及ぼしている。
緊急事態宣言や外出自粛がなければ生まれなかったアートがあるかもしれない。ウィズ/ポスト・コロナ時代のアートは鮮烈だ。コロナを経て、世界の、そして日本のアート作品は今後どのような変化を見せるのだろうか。そのヒントが本書に書かれている。
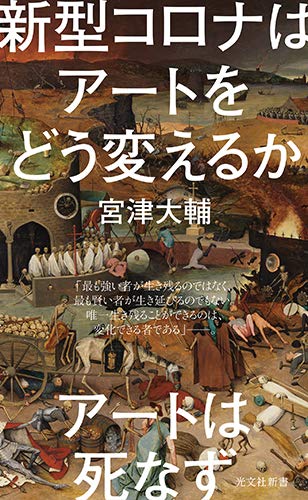
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.