BW_machida
2021/08/31
BW_machida
2021/08/31

4度目の非常事態が宣言されたかと思えば、それもまた延長され、これまでまことしやかに言われていた「医療崩壊」が、がぜん現実味を帯びてきた。連日のようにTVでは、自宅療養などと言って体良く放置された感染者の病状の急変~死亡がニュースとなる。
そんな政府の慌てふためく様が、これからも繰り返し来るに違いない伝染病の脅威に晒される暗澹たる未来を人々に予感させる。
そんな折に、『「孤独」という生き方』(光文社新書)を手に入れた。著者は、ノンフィクション作家の織田淳太郎氏。長くスポーツの世界や精神医療の分野をルポルタージュしてきた著者が、最愛の息子を亡くしたことを契機に生き方を変え、独り人里離れた山荘に暮らしながら自己の求めるモノを見つめなおす赤裸々なレポートである。
「孤独」から逃れるという「孤独」にさえ耐え切れず、さらに深い「孤独」へと身を隠す。
この衝動に駆られた自暴的な選択、そして息子を失ったことで唐突に始めた山の生活が、その後の私の心にどんな変化をもたらしたのか。(中略)
自らの死をも希求していた私が、なぜ「癒し」という思わぬ活力を得ることができたのか。しばらくその理由がわからなかったが、とにかく私は少しずつ笑顔を取り戻し、以前とはまるで違う穏やかな自分がそこにいるのを、やがて見出すようになった。
プロローグに吐露された、自らの死をも希求し、人里離れた山中の庵に心地良さを感じながらも懊悩を続ける著者が、自分にも似た疲れを抱えた人々や動物たちとのささやかな交流を描いていく。
そうして、いつしか逃れようとしていた人の営みの手触りを確かめながら、かつてとは違った生き方を見つけた主人公が、それでも離れようとはしない新しい居場所の心地良さの正体を探す。そんな一冊だ。
まだ30歳にもならない息子が、2年5カ月の闘病生活の末にこの世を去り、その3週間後には、標高850メートルもの山中にある禅寺に身を寄せる。TVはおろかラジオすら無い緘黙の地には、携帯の電波も届かない。そんな古寺で、住職から教えられた座禅を気ままに組んでは懊悩する日々を繰り返す。
「あらゆる苦しみは、自分は肉体だという思い込みから生じていると思うんです。この世には病があり、老いがあり、死があり、ほとんどの人がそれに怯えて生きている。これは肉体と自分を同一視することによって生じる恐れだと思います。
しかし、肉体を構成する分子や原子といった物質、言い換えれば、所有するものが自分から一切なくなったらどうなるか。そこには、哀しみも苦しみもなく、生じるものも滅するものもない、まさに般若心経のような世界が待っているはずなのです。私はそこに本当の意味での解放があると思うんです。
実際、自分をそういう状態に持っていくことが、座禅の目的だとも言われています。自分の肉体が消滅したことを感じ、そこに留まる。それが『涅槃に入る』という意味だと、私は捉えています。
まだ山中の庵にたどり着く前の著者が、身を寄せた禅寺での座禅三昧の日々の中で、住職が語る座禅の解釈と、それにより得られるかもしれない境地が、とても分かり易く語られている。これも、著者がいかに優れたノンフィクション作家であるかを示す証左であろう。
そうして本書は、自らを「自分に嘘をついて生きてきました」と語る住職や、娘の死を悼んで田舎暮らしを始める中年女性や、そんな田舎暮らしを求める人を顧客とする不動産会社の社長や、国立公園内で隠遁生活を送る「仙人」と呼ばれる老人などを取材し、それぞれがそこに至るプロセスを物語っていく。
そんなノンフィクション作家としての生き方と、山中の庵に居場所を見つけた主人公の暮らしぶりが物語を織りなして行く。
「できれば、誰もいない高台の緑豊かなところがいい」
私の希望を受けて、その小さな不動産会社の社長が最初に連れて行ってくれたのは、禅寺から西に40キロほど離れた標高460メートルの別荘地帯にある山荘だった。(中略)
一帯にはこの山荘も含めて6軒の別荘が、森の茂みに隠れるように点在していた。そのうち2軒は完全な廃墟。あたりは静寂に包まれ、野鳥の澄んだ囀りとせせらぎ以外、私の耳に届くものもない。
「ここを自分の庵としたい」_。
そう思った。
そこから山荘を購入するまでの経緯には、夫人とのリアルなやり取りなど、これから田舎暮らしを考えようとする方には是非参考にしていただきたいトピックスが並んでいる。
そして始まった山荘暮らしの中で、望みのままに静謐な時を過ごすと同時に、生活者としての様々な問題が起きる。倒れるままにしておけば、山荘の屋根を直撃するに違いない直径30センチ、高さ8メートルにも及ぶ松の木の伐採や、枯れたり濁ったりを繰り返す取水口の問題など、そのままにしておけば心地良い全てを破壊する問題ばかりだ。
思いつくままに移り住んだ主人公には、とても解決できそうにない諸問題を解決するべく、地元役場の職員との折衝や、近隣(とはいえ相当に離れている)の別荘に住む、田舎暮らしの先輩との共同作業など、人里離れた山中で交わされる互いにわきまえた心地良い範囲の交流など、単なるノウハウ本やガイドブックでは教えてもらえないやり取りがリアリティ豊かに描かれている。
「自然ほど恐ろしいものはない」という声もあるが、台風や地震がもたらす自然災害は、単に膨大なエネルギーの極から極への移動の結果にすぎず、私たちを殺すために発生するのではない。それは、ただそこに「在る」だけ。(中略)
庭先や野に咲く花は、栄養が枯渇すれば萎み、水がなくなれば枯れて死んでいく。私たちがその世話を怠っても、誰を責めるわけでもない。命の根を切断された切り花にしても、わずかな間、人間の心に彩を与えると、文句も言わずにその短い命を閉じていく。それも、ただそこに「在る」だけ。
野生動物や野鳥たち、そして小さな虫たちも、価値判断に囚われることなく、一瞬一瞬を糧として「今」を生きている。
読み進めるうちにたどり着いたその一文には、本書の冒頭で著者が記した「独り在ること」に通ずる、「在る」こととはどういうことか…。
それを著者は、解釈として記しているが、答えのように感じてしまうのは決して私だけではないように思う。
本書『「孤独」という生き方』(光文社新書)は、決して「田舎暮らしのススメ」などではない、人生の終盤に出会うかもしれない生き方に対するノウハウ本だった。
文/森健次
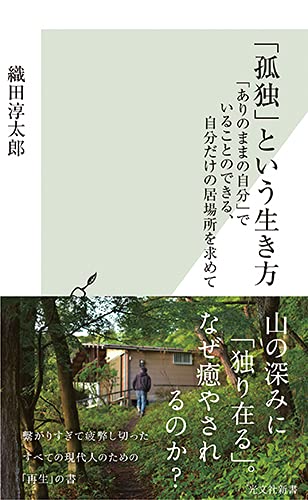
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.