ryomiyagi
2020/02/07
ryomiyagi
2020/02/07

2019年12月21日。この日は捕手にとって(及び捕手に関与する者にとって)、忘れることのできない日となろう。
衝撃的な第一報はAP通信からだった。
「米大リーグ機構(MLB)と審判員組合が2024年までの労使協定で、コンピューターによるストライク、ボール判定を将来的に導入することで合意した。」
「その日」はいつか訪れると想定(いや、覚悟と言うべきか)はしていた。ただ、技術的障壁、ストライクゾーンの再定義の必要性、現場の反発等、実装へのハードルは極めて高い。「まだしばらくはかかる。現場も簡単には認めないだろう。」とタカをくくっていた部分もあった。
そんな中での今回の報道。Xデーは予想よりも遥かに近いようだ。想定レベルと言えど具体的な日取りを提示されると、「遠い先の想像」は途端に「近未来のリアル」として体感される。
MLBのトップ、ロブ・マンフレッドコミッショナーに言わせるとこうだ。
「球審はイヤフォンから判定を聞くため、ファンの視点からは試合の見た目に変化がない。それが重要だと考えている」なるほど。「見かけは今までと変わらんから、どうせファンも納得しよるわ」と。就任以降様々な「改革」を断行し、観客動員数を500万人も減少させた「実績」を持つコミッショナー様の御言葉は実に重いものである(笑)
球審のロボット化は、これまで行われた「改革」とは次元の違うものだ。球審の業務縮小、それに伴う代替性上昇(≒専門性低下)、ストライクゾーンの極端な拡大とそれを活かした投球の変化……、球界にとって未曽有の変革となる。
その中でも私が特に重く見ているのが、捕手による「フレーミング技術」の消失だ。球審のストライク判定に捕手の捕球技術が普遍的かつ継続的に影響を与えてきたのはもはや常識レベルの話で、毎年この技術により年間40~50点の差が選手間で生まれる。コールがオートマチックに行われるなら、この捕手による”presentation”はまるで意味を成さない。野球における最大数を誇る守備行為、この職人の技術が「ルール」によって一瞬で消し去られることになる。
この問題に関しては多くの意見がある。「そんな所、別に興味ない」「本来必要のない技術だ」「誤審が減る方が有意義だ」等々。テーマがテーマだけに議論が多くて当然だろう。
ならば、この機会に「こちら側」の主張も残しておくべきだ。フレーミング技術の価値・重みを少しでも考えてきた一人として、何を守り、何を残していきたいのか。いくつかの論点に分け、私見を述べたいと思う。
大テーマ「判定の機械化」が俎上に載る時、真っ先に、そして最も熱く主張されるのが「人間味の消失」という点だ。判定の正確性を追求するのであれば、機械化に勝る術はない。
常人では目で追うことすら難しい速度で発生するイベントを、人間の肉眼で全て正確無比にジャッジするのは不可能だと断言できる。「でもそれでいいのか。間違える可能性があろうと、自チーム、相手チーム、そして審判、フィールドの「人間」によって繰り広げられる予測不能のドラマこそが大事なのではないか。」リプレイ検証、チャレンジ導入、先に行われた「改革」の際にも何度も見た議論の構図だ。テクノロジー化の波、ゲームの高速化の流れ、そんな現代野球界においてはクルーシャルな問題だと私も強く感じている。
が、誰でも想像に難くない、既に語りつくされたトピックであるためここでは多くは語らないこととする。この点ばかりが話題にされることで、本件(球審の自動判定)を、リプレイ検証や申告敬遠導入と同じ構図で捉えてしまうと本質を見誤る。ここから先が本題である。
繰り返しになるが、本件は従前の「改革」とは全く別の問題を内包している。それこそが本コラムの主題、ロボット審判によって葬られるフレーミング技術の問題である。
問題の重要性を体感してもらうために、前提としてフレーミングとはどういったものかについて説明したい。
フレーミングの機会は、一人の捕手で年間最大8000回以上にも及ぶ(参考までに、内野手の守備機会は数100程度である)。多くの観戦者には意識すらされないが、野球において最も多く遂行される守備行為なのだ。
重要なのが、このプレーの成果はランダムに現出するわけではないという点だ。数値が高い選手/低い選手は、例年(完璧にとまでは言わないまでも)ある程度同じ顔ぶれが並ぶ。要するに、「できるやつ」と「できないやつ」が明確に出るということだ。誰もが普遍的にできるわけではない、その固有性にこそ価値がある。それが「技術」「スキル」だ。
技術とはプレイヤーの研究と鍛錬の結晶である。現在の選手にとっては血の滲む努力の末体得した無形の資産であり、未来の選手にとっては己の夢と可能性を秘めた投資機会である。過去の努力と未來の可能性が、観戦可能な現在のプレーとともに消え去ろうとしているのである。常人にはできない技巧、プロならではの技術こそが、プロスポーツの商品価値の源泉ではないのか。
「そんな所、別に興味ない」という意見もあるだろう。しかし、あなたに興味がなかろうと、少なくない数の興味を持つ人、これから興味を持つ可能性のある人、そして実際にプレーとして体現している選手がいる。厳然と存在する「技術」に内在する無形の価値と無限の可能性は、プロスポーツとして絶対に護るべきものではないだろうか。
球界のスーパースターからも同様の声が上がっている。3度のサイ・ヤング賞に輝いているマックス・シャーザーは、フレーミングがなくなることが「最大の問題」だと語った。同じくCY賞3度受賞のクレイトン・カーショウは、フレーミングの名手の仕事が奪われることを問題視した。
リプレイ検証を導入しても、申告敬遠を導入しても、ここまで明確に失われる技術はなかった。年間30万回ものプレーとそのための努力が一瞬で無に帰す、この点で今回の議論は全く別のステージに達していることを認識してほしい。
「ルールでストライクゾーンが定義されているのだから、ルールの穴をつくフレーミングは、“本来”不要な技術なのではないか」
これも重要な論点だ。ルール上定義されたゾーン判定を機械により忠実に実行する、「あるべき姿」としてのルールの遂行可能性を高める、これは判定自動化の正当性を担保する主張と言える。
そもそも、「本来」とは何だろうか?「ルールブックに書かれたことが忠実に再現されるべき『本来の姿』である。」というのが普通の考えだろう。それならば、そのルールは実行可能であることが最低条件である。
だが、現実はどうか。時速150キロで向かってくるボール、手元で急激に変化するボール、打者によって異なる体格・姿勢・立ち位置、その中で忠実にルールブック通りの五角柱をミスなく見切ることが人間に可能か。答えるまでもない。かくして、年間数万回もの「誤審」が起こることとなる。
要するに、現状のルールブックは、現実には実行されることが全く想定されていない(あるいは来る日のテクノロジーの力によってしか遂行され得ない)全くもって破綻したものだと言える。他の競技でも人間が裁く以上完璧とはいかないものだが、これだけの規模で「誤審」を起こしてしまうなら、そもそものルール設計に問題がある。そんなものが、「本来の姿」などと果たして言えるのか?
では、結果論としてテクノロジーがルールブックに追いついた今、どういう道があるのか。一つは、機械が人間を押しのけることで、およそ達成できるはずのなかった「ルール」を野球史上初めて実現可能にする道だ。現在進もうとしている方向である。しっかり定義された枠の中で正確にゲームを進めたい、というのも一つの道だろう。
ただ、私ならこういう道を提示する。
「ルールに縛られるのではなく、ルールを変えろ」
ルールとは、ゲームを円滑に進めるための手段であり、目的ではない。野球という競技の魅力を最大化させるためならば変更の余地は十分にある(それこそマンフレッド氏がこれまで何度も断行してきたように)。必要とあらば、そんなものぶち壊してしまえばいい。
私の主張はこうだ。「ストライクゾーンの定義」など必要ない。代わりに、「ストライクの定義」を「審判がストライクと判定したもの」として設定し、そのための「目安・絶対努力義務」としてゾーンの枠を設定すれば十分だ(ただし判定の事後的な検証は、過度に恣意的な判定の乱発を防ぐために必須だろう)。これで競技の機能性が損なわれることはない。なぜならこれこそが現状そのものだから。
数十年間およそ形にすらなっていないルールが、技術や仕事、多くの人間の可能性を奪ってまで後生大事に護らなければならないものなのか。それが本当に野球の進歩なのか。より根本的な所から考える必要がある。
いずれにしても、「(存在すらしない)「本来の姿」をどう実現させるか」という発想で考えてはいけない。着地点、ゴールを前提条件として当然かのように設定されてしまうと、無意識に「どうやって戻るか」とそこに引っ張られてしまうものだ。
行うべき議論は、「ゲームをより魅力的なモノにするために何が最適か」である。テクノロジーが追いついたこの段階で、ルールを再構想するような発想だ。その結果、「枠を設定して機械でギチギチに運用するのが野球のために良い」、という結論になるならばそれも一つの答えだろう。
「変化をもたらす際には反発はつきものだ。申告敬遠導入の時だって反発はあった。でもやってみれば皆気にしなくなった。今回も同じだろう。」といった声もある。
ただし、物事はそう単調なものではないのではなかろうか。技術が消えた世界では、その技術自体が認知されないのだから反発の声がないのは当然であり、おそらくそこに収斂していく。私のような意見は間違いなく「古臭いマイノリティ」の烙印を押されることになる。しかし、確かに「そこにあったもの」がなくなる。現状どれほど大きなインパクトを持つ技術なのか知れば知るほど、「なくなったもの」の大きさを鮮明に認識できる。
そのために本コラムを書いた。一人でも多くの人に知って欲しいから。一人でも多くの人に興味を持って欲しいから。無数の血と汗と涙の末、創り上げられたモノが存在していることを。今まさにそいつが消滅の危機に瀕していることを。
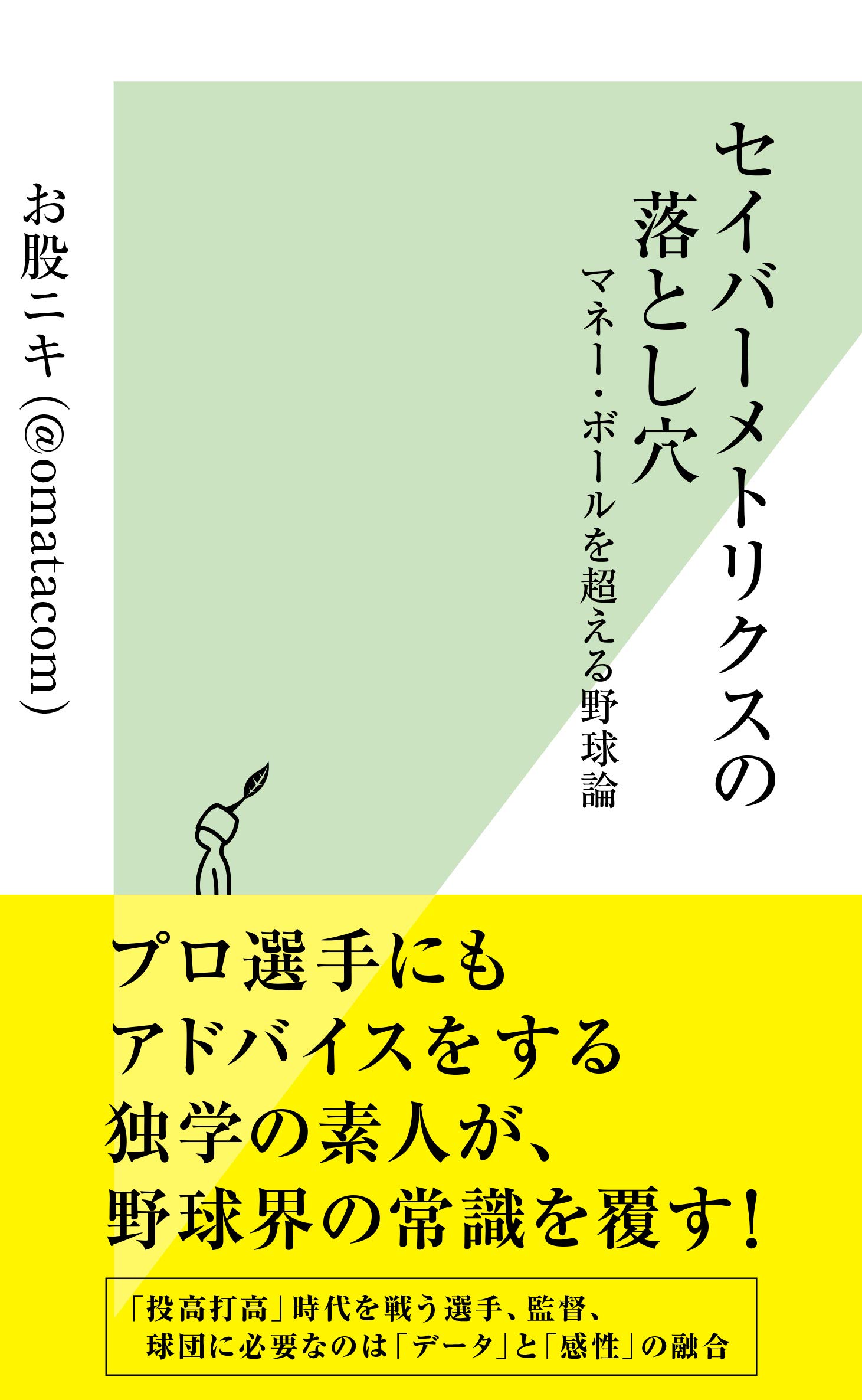
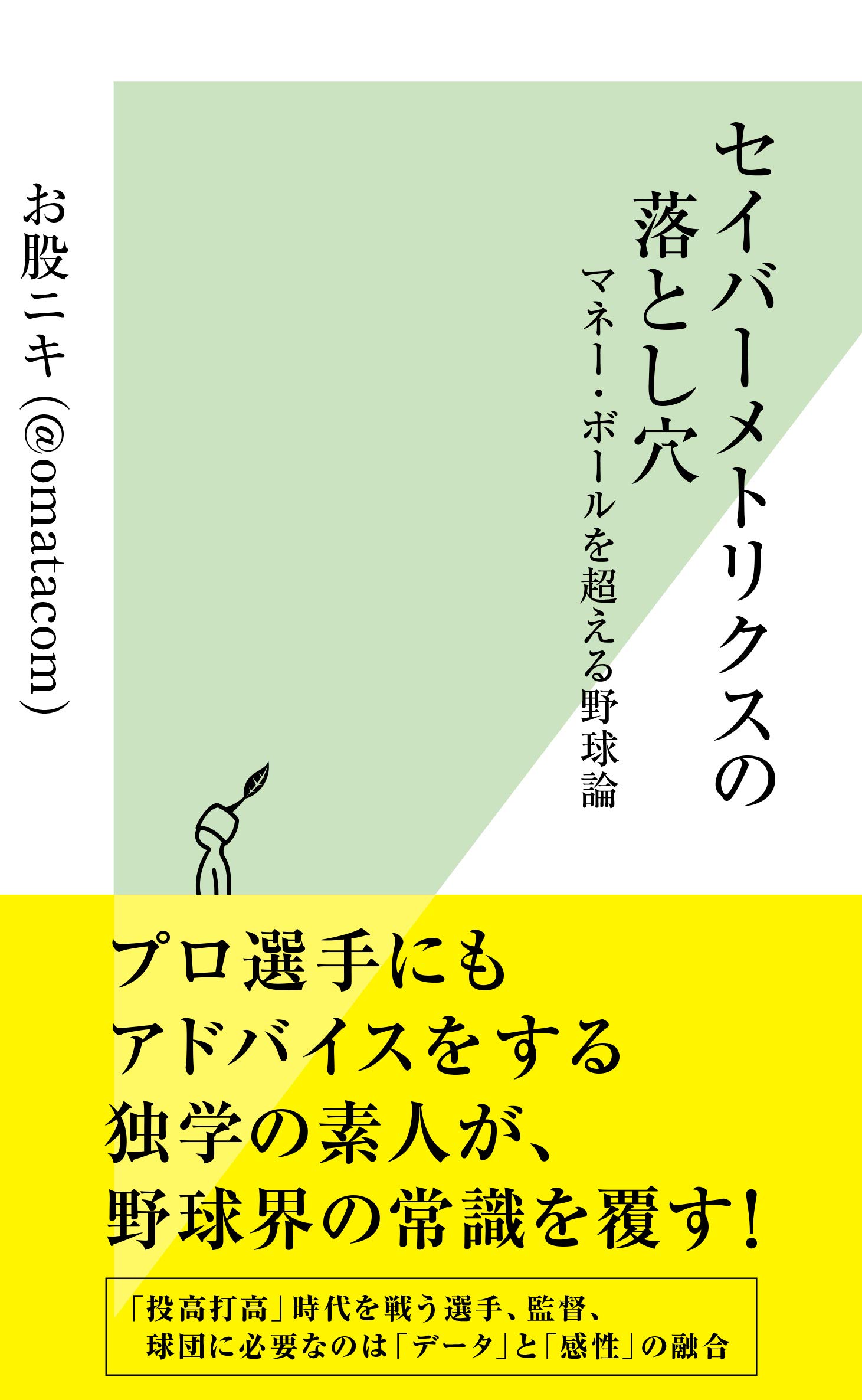
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.