ryomiyagi
2020/03/25
ryomiyagi
2020/03/25

2002年のある日、当時プライベート・エクイティ・ファンドの財務担当重役だったローズ・マーカリオは、リムジンでニューヨーク市内を移動中、渋滞に巻き込まれた。ニューヨークに来たのは、新たな投資ラウンドの資金調達が目的だった。やがてのろのろと進んでいたリムジンが止まった。マーカリオの口から、いらだちのため息が漏れた。窓の外に目をやると、原因がわかった。「見るからに精神疾患を抱えた人物が、道路を横断しようとしているせいだった。[中略]その人物は道路の真ん中で、ぐずぐずしていた」。
自分の母親が統合失調症だったマーカリオはそれを見て、すぐにぴんときた。しかし時間が刻々と過ぎるにつれ、しだいに我慢できなくなってきた。この人物のせいで「待たされている。こんなに急いでいるときに」という思いが募った。そのときふと「窓に映った自分の顔が目に入った」。怒りでこわばった自分の顔を見ると、とっさにドライバーに車を道路脇に停めさせ、車から降りた。「そのままセントラルパークまで歩いて、緑のある場所に行き、わが身を振り返った。今のわたしはこんな人間なの? 成功するとはこういうことなの?」
これはまさに触媒的な問いになりうる問いだ。そこにはすべてを一変させる力が秘められている。しかしわたしたちはこのような体験――呆然としたり、自分を高められる可能性に気づいたりする体験――をしても、結局、何も変わらないことが多い。ほかのことに注意を逸らされたり、変化に伴う犠牲や苦労に恐れをなしたりして、気分はいつしか冷めてしまう。
マーカリオはちがった。彼女は実際にその仕事を辞めた。そして、悔いのない一生を送るためには何を仕事にしたらいいのかを、時間をかけて真剣に考えた。その結果、職種を大きく変えることにし、最終的には、持続可能性に力を入れている企業、パタゴニアから最高財務責任者への就任を要請されると、それに応じた。五年後にはCEOに就任し、現在に至っている。
ローズ・マーカリオの話を紹介したのは、パタゴニアのことが頭に浮かんだからでもあった。ちょうど少し前に、パタゴニアの歴史について、同社の人から話を聞いたところだった。その歴史は、物質主義の世界に背を向けたサーファーでロッククライマーだったイヴォン・シュイナードが、思いがけず実業家になったときに始まる。実業家となった彼の胸に浮かんだのは次の問いだった。魂を売り渡さずに生計を立てるにはどうすればいいか。
シュイナードはこの問いに強く心を捉えられ、それから何年ものあいだ、その答えを探り続けた。やがてどうすれば自分の信条とビジネスとのあいだに折り合いをつけられるかを見出し、それらの緊張関係は耐えられないものではなくなった。しかし自分が創業した会社が成長するにつれ、第二の問いが浮かび上がってきた。それは、そのような緊張関係を気にするリーダーはどういう会社を築けばいいのか、という問いだ。
この頃には同時に、さらに大きな緊張関係が生じ、それとも向き合わなければならなくなっていた。シュイナードの会社はもともとアウトドアライフに対する自身の愛にもとづいて創業された会社だった。それが急速な生産や流通の拡大に伴って、環境を破壊していいのか。環境への影響を最小限に抑えるにはどうすればいいのか。パタゴニアはこの問いに奮起し、それから何年もかけて、オーガニック素材への移行というむずかしい取り組みを大きく進展させた。
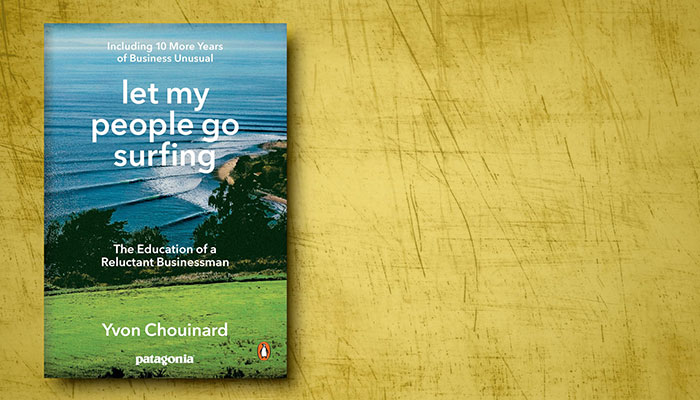
その後、パタゴニアの野心(と問い)は次のように拡大した。地球への悪影響を減らすだけに留まらず、地球への悪影響を実質的にゼロにするにはどうしたらいいか。それも、環境だけではなく、社会への悪影響も出ないようにするには、どうしたらいいか。さらには環境によい影響を与えるにはどうすればいいか。そこまで来ると、経済的な繁栄のためには代償を払わなくてはならないという社会の通念に対しても、問いを投げかけることになった。
とはいえ、パタゴニアはアパレル業界の大手企業と比べたら、まだまだ小さく、巨大産業の中では脇役だった。自分たちが身を正すだけで満足していていいのか。社内では、自社と反対方向に進んでいる世界のアパレル業界に変化を起こすには、自分たちは何をすればいいのかという問いが口にされ始めた。直接的な競合関係にある他社にも環境に配慮させるにはどうしたらいいのか。これはパタゴニアの古参の社員にすら、いくらか度を越しているように感じられた。消費者のあいだでパタゴニアは持続可能性に力を入れているところがほかの企業とはちがうと認知されていたからだ。当然、社内には次のような心配をする者がいた。「もし他社に追随されたら、競争上の強みを一つ失うのではないか」
その問いは社内でさらに次のようにひっくり返された。「もし他社が追随しなかったら?」。「もしわれわれが本気で環境を守りたいのなら、他社にまねされることはむしろ歓迎すべきではないだろうか。それどころか、パタゴニアには環境対策についてのノウハウを公開する義務があるのではないか。われわれと同じことをしようとする企業を積極的に助けるべきではないのか」
ローズ・マーカリオがパタゴニアに加わったのはちょうどこの頃だった。パタゴニアのそれらの問いはマーカリオには、次の四半期の損益にばかり注目する証券業界の問い、彼女の言葉を借りれば「一株当たり当期利益という鎖を首に巻かれた」業界の問いよりも、はるかに自分の信条と一致し、意義深いものに思えた。こうしてマーカリオがパタゴニアへの加入を決めたことに示されているとおり、企業が問う姿勢を持つことには、問題を解決できる優秀な人材を引きつけるという利点もある。マーカリオは今、CEOとしてそういう問う姿勢を推し進め、問いをさらに次のように拡大させている。「他社にまねされないことが不快に感じられるようにするにはどうしたらいいか」
このようなパタゴニアでは当然、社員たちは今も、あの最初の触媒的な問いの答えを熱心に探求している――魂を売り渡さずに生計を立てるにはどうすればいいか。これはいつまでもわたしたちを刺激し続ける永遠の問いだ。多くの幹部社員との会話を文字に書き起こしたものを読み直していて、わたしはあることに気づいた。それはなんらかの一つの習慣とか、創造力を高める訓練とかによって、問いの意欲がかき立てられ、維持されているわけではないということだ。そうではなく、核となる文化的な価値観とそれにもとづいた行動によって、問い(と答え)の活発さは保たれている。
例えば、そのことはパタゴニアの人事とシェアードサービスの統括担当副社長を務めるディーン・カーターとの会話からはっきりとわかった。わたしはカーターから、パタゴニアが他社に先駆けて、従業員の年次査定で相対評価をやめたときのことについて教えてもらった。今では相対評価をやめるのが企業のトレンドのようになっているが、パタゴニアではそれは業績管理で何をめざすべきかという問いを深く考えた結果だったという。
カーターの話でわたしが何より感銘を受けたのは、「本社内に託児所を設ける」というやはり従業員のことを考えたまた別の決定についての説明だった。それはふつう「当たり前」の決定とはいえないだろう。現に、託児所を設けている企業はいまだにきわめて少ない。ところが、カーターによると、パタゴニアではそれは誰からも「当たり前」の決定と受け止められたという。
カーターは2015年にパタゴニアに加わる以前も他社で人事の仕事をしており、従業員の勤怠の問題に詳しかった。ギャラップ社が毎年行っている米国の労働者の勤怠に関する調査には由々しい実態が示されている。2015年の調査では、「仕事に熱心に励んでいる」と答えた人が3分の1以下に留まるいっぽう、「熱心に励んでいない」と答えた人は51パーセントにのぼった。さらに「積極的に仕事を避けている」と答えた人も17パーセントいた。カーターはこのような事態を改善するため、どこの企業に勤めていたときも、人事部門のトップとともに「従業員が仕事にもっとやりがいを感じられるようにするにはどうしたらいいか」という問いに取り組んでいた。
パタゴニアに勤め始めて数年経ったとき、カーターはその問題をはじめ、人事の問題について、自分がそれまで「情けないほど」狭い範囲でしか考えていなかったことに気づかされたという。ちょうどそのとき廊下を、ひとりの従業員がベビーカーを押して歩いてきた。カーターはそれを見て、いった。「自分を情けなく感じた大きな理由は、あの小さなベビーカーです。20年も人事の仕事をしていながら、勤怠や男女平等の問題の単純な解決策がこんなに身近にあるとは、それまで思いもよりませんでした」。社内託児所の問いをそれらの問題の枠組みの中に置いてみれば、「答えは簡単に出たんです」とカーター。「それがわかっていれば、もっと昔から託児所の設置を呼びかけていましたよ!」
わたしは長年、企業の内部を見ているが、パタゴニアは真実を追究している会社だと断言できる。社員は社内外を問わず、「徹底的な透明性」を大事にしている。その徹底ぶりは、エクストリームスポーツを思わせるほど過激なレベルだ。パタゴニアは問題を解決しよう、真実を探そう、主体的に行動しよう、他者を気遣おう、変化を起こそうという姿勢の人々を採用している。そして採用後は、長期的な利益や目的や努力には短期的なコストがかかることを承知のうえで、それらの情熱家たちを全力でバックアップする。そういうコストにはまったく頓着しない。
ローズ・マーカリオに話を戻そう。素材開発部門のシニア・ディレクターを務めるマット・ドワイヤに聞いた話から察するに、マーカリオは今後も、ぬかりなくこういうことをすべて続けていくだろう。経験豊富な科学者で、手法でも、撥水生地などの素材でも、従来からあるものはなんでもまずは疑ってかかるドワイヤは、次のように話している。「ローズはわたしが知っているリーダーの中で誰よりも、不快な質問をすることに長けています。納得できる答えが返ってこなければ、容赦なく指摘もします」
変ないい方になりますが、とても感じのよい尋ね方で、なおかつ不快な質問をするんです。そうとしか表現できません。わたしはここへ来てからずっと、それをまねようと努力していて、いつもそういう質問をしようとするのですが、どうしても回りくどくなってしまいます。わたしが質問を二、三回、重ねなくてはいけないところを、ローズは一つの質問で済ませます。不快な質問をし、問題の根を掘り起こし、次に進みます。解決できれば解決し、解決できなければ、次のようにいうだけです。「この失敗にはもう処置の施しようがないわね。これはここでやめておきましょう」。そういう部分はとてもてきぱきとしていて、迷いがありません。
パタゴニアでは、最初の問いによって放出されたエネルギーは、その問いによって示唆されるさらに大きな次の問いを探すことに振り向けられている。問いを手がかり、足がかりにして新しい高みへとのぼり続けているのだ。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.