2019/01/18
田崎健太 ノンフィクション作家
『戦艦武蔵ノート』岩波書店
吉村昭/著

昨年末、旧知のPRプランナーであり、コラムニストである、中川淳一郎さんに誘われて、ウェブメディアのライター忘年会に参加してきた。
中川さんからは「彼ら、彼女らは紙媒体のライターと違ってキラキラしてますよ。そして田崎さんが最年長であることは間違いないです」と脅しめいた言葉を掛けられていた。中川さんによると、しかめ面で斜に構えていた紙媒体の記者と違って、彼らはファッション誌誌の「読者モデル」のように自らの存在を押し出し、楽しそうに仕事をしているという。
正直なところ気は進まなかった。ただ、どんな人たちがいるのだろうという興味もあり、中川さんの誘いに乗ることにしたのだ。
新宿・歌舞伎町の雑居ビルの地下の会場には、二十代から三十代と思しき、男女が集まっていた。若いライターがいないと知り合いの雑誌編集者が嘆いていることを思い出した。新聞や出版社を中心とするライターの系譜とウェブライターは断絶しているのだろう。
中川さんは次々と若いライターを紹介してくれた。彼らと話してみて、ぼくは拍子抜けした。実に感じがいいのだ。
何人かはぼくの著作を読んでいた。『真説・長州力』について熱く語る人間や、『全身芸人』についての話にもなった。
一人の女性ライターからは「取材前、質問リストを作っていますか」という質問を受けた。ぼくは、かつては作っていたけれど、今は必ず聞かなければならないことをメモすることはあっても、リストは作っていないと答えた。
ぼくは重要な被取材者に対しては事前に年表を作っている。その年表を作る過程で自然と何を聞くべきか頭の中でまとまっている。わざわざ書き出す必要はないのだ。
ただし、仕事を始めたばかりの段階ではどういう答えが返ってくるのか、想定しながら質問リストを作ることはいいと答えた。そして、自分が思っていたような答えしか返ってこない取材ならば失敗だと考えたほうがいいと付け加えると彼女は「どうして、ですか?」と驚いた顔をした。
これはぼくが週刊誌の編集部時代に叩き込まれたことである。聞く前から答えが分かるような薄っぺらい取材はするな、ということだ。
そう理由を説明すると、彼女は「そうなんですね。勉強になります」と感じ入ったような表情で小さく頭を下げた。ああ、彼女たちに取材のやり方を教える編集者、あるいは先輩の書き手がウェブの世界には、あまりいないのだなと思った。
ぼくたちの時代はつまらない企画を出せば、目の前で上司に破られることも、罵られ物が飛んで来ることも普通だった。その中で必死で頭を捻った。そして夜、酒場に行くと他社の編集者や、作家から様々なことを教わった。それが今のぼくの血肉になっている。
そして、彼らは読むべき本をぼくに教えてくれた
例えば、吉村昭の『戦艦武蔵ノート』(岩波現代文庫)である――。
この本は吉村が一九六六年に発表した記録文学の傑作『戦艦武蔵』をどのように取材したのかを明かした書である。
戦艦武蔵が沈没するときに居合わせた人間の話を聞いたときだ――。一通り、事前に準備した質問を元に話を聞いた後、彼は海に飛び込んだ人間には傷を負った人間が少なくなかったと言った。吉村は傷という言葉に反応した。
〈私も疲れていたが、何気なく、
「なぜ傷を負った者が多かったのですか?」
ときいた。
「当たり前じゃないですか。牡蠣にやられるんですよ」
「カキ?」
「艦底には、牡蠣やその他いろんな貝殻がついているじゃないですか」
氏は、苦笑しながら言った〉
この言葉で吉村は戦時中、目にした一五〇トンの古びた木造船のことを思い出したという。船底一面に、おびただしい牡蠣が貼り付いていたという。食糧不足の頃であったので、その牡蠣は貴重な食料となった。
一五〇トンの船ですらあのような牡蠣がひりついていたのだ、武蔵の船底には附着した貝や海藻の量は膨大なものであったに違いない。吉村はこの牡蠣という身近な単語を耳にして、作品で描くべき武蔵の像が大きく膨らんだと書いている。
その上でこう続ける。
〈この折の経験は、私に一つの信念を与えた。私は小説を書くとき、その裏付けとして取材をするが、まず他人の書いたものを全面的には信用しない。自らの足で歩き自らの耳で聴くことに徹する〉
そのため、吉村は編集部から取材を編集者に分担させましょうかという申し出を断るようになった。
〈編集者の仕事は多忙をきわめ、私のために時間と労力をさいてくれる余地はほとんどないはずである。第一、私に与えられた仕事は、私自身の仕事であり、第三者に迷惑を掛けることは許されないはずである。そうした常識的な考えと同時に、私がその好意的な申し出を辞退したのは、些細な話の中にも思わず創作意欲を刺戟する貴重なものがひそんでいことを私自身が知っているからである〉
吉村はあくまでも事実を元に自らの想像力を使って作品を組み立てる小説家であり、ノンフィクション作家ではない。しかし、『戦艦武蔵ノート』を読むと、取材に対する真摯な態度、丁寧さ、細やかさに目を見張るだろう。ぼくもたまにこの本を開くと、背筋が伸びるような思いになる。
フェイクニュースが跋扈し、取材をせずに安易に書かれた記事がネットには氾濫している。新聞社や出版社が繋いできた、きちんと取材して書くという流れが途切れがちな今だからこそ、多くの人に読まれるべき一冊である。
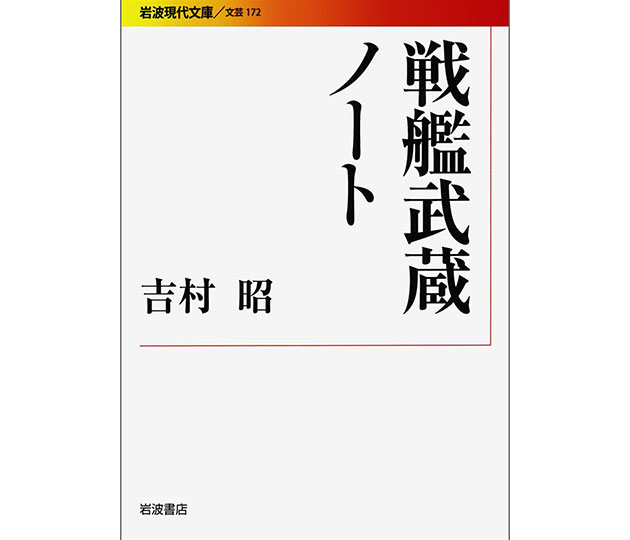
『戦艦武蔵ノート』岩波書店
吉村昭/著

