2019/02/18
藤代冥砂 写真家・作家
『孤島の祈り』集英社
イザベル・オティシエ/著
旅をテーマに含んだ小説やノンフィクションを読むのは久しぶりであった。遠ざけていたつもりはないが、その辺の旅小説が描く事柄なら、すでに多くの現実の旅を通して経験済みであり、わざわざ貴重な時間を費やす価値などないと生意気にも考えていた、というのが偽らざるところだ。
なので、たまに読む旅本は、こんな旅はしたことないし、するつもりもない、と予測できる冒険譚に限られていた。例えばチベットの奥地で幻の湖を探すといった類の話をである。
旅と一口に言っても、それは年齢や経験値によって情熱の注ぎ方や向き先が異なる。若く知的好奇心を満たす情熱に満ちた頃には、旅先での新しい出来事がそのまま肉体化するようなダイナミズムがあり、解釈する間もなく、対象へと無鉄砲に飛び込んでいく姿となる。一方、子供を育てあげ、人生のコーナーも既にいくつか曲がり切った年齢での旅は、必然的に回顧的であり、趣味的であり、暇つぶしに終始しがちになる。
これは実際の旅についてであるが、読書の旅もそれを反映する傾向があると思う。
今回選んだのは、いわば遭難ものである。パリで満ち足りた日常生活を送っていた30代夫婦が一年の長期休暇を取り、船で大西洋を南極方面へと南下していく旅の物語である。何不自由ないどころか、経済的にも社会的にも恵まれた部類に属する生活に不平があったわけでもないのに、「一生に一度くらい、濃密に生きてみたい」という衝動を抑えきれずに、安定した人生の祝祭的な羽目外しで始めた旅が、思わぬことになる。
もともとこの夫婦は登山やアウトドアスポーツを趣味としていて、日常から外に出ることには慣れていた。とはいえ、いわゆる冒険家からはほど遠く、週末キャンプを楽しむ程度の一般人である。ストーリーの大筋はその二人が南極に近い孤島に取り残される話である。
ともなれば、文明から突然遮断された二人の行動や思考を通して、インターネットをはじめ、様々なコミュニケーションツールで地球の隅々まで繋がっている現代人の暮らしや幸福度について考察するような教訓的な読後感を予想しがちだが、この作品のインパクトはそこにはない。
もっと生理に寒々しく直接刺さってくる痛みのある作品である。二部構成の、前半のタイトルが「むこう」であり、後半が「こちら」になっているように、生還してからの物語が前半の冒険譚の過酷さをある意味上まっていて、「こちら」に住む大方の読者にとって自分のストーリーとして胸に迫ってくる。
喪失からの帰還への旅。この小説が描いているのは、心の旅であり、だからこそこの過酷な旅に同行できるのだ。
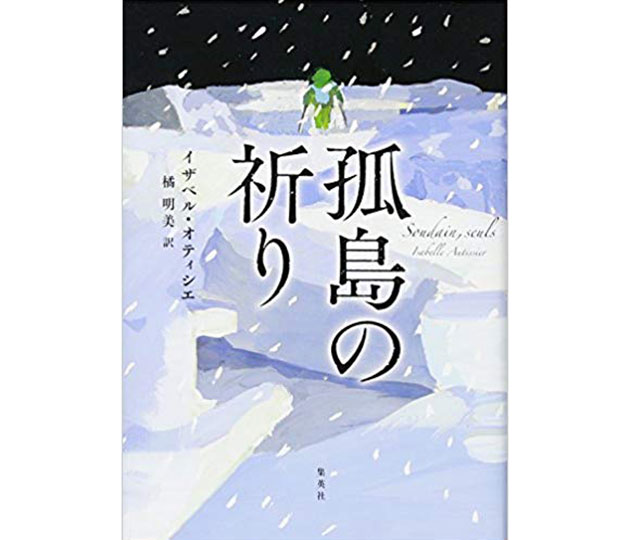
『孤島の祈り』集英社
イザベル・オティシエ/著

