2019/05/30
清水貴一 バーテンダー・脚本家
『ゴリラの森、言葉の海』新潮社
山極寿一、小川洋子/著

恥ずかしながらわたしは日本語しか使えない。お店に来店する外国人の多くは、どなたも一様に優秀である。日本語をある程度理解しているし、中には流暢な日本語で酔っ払うツワモノまで存在する。わたしはそれをいいことに、彼らの母国語にはまるで関心を示さずにいるわけだが、もしもお客さんが言葉のまったく通じない相手ばかりだったら、きっと仕事どころではない。言葉の解らないバーテンダーと母国語しか話せない外国人。わたしが海外旅行で陥る状況だ。言葉の通じないもどかしさや心細さは、みなそれなりに経験があるだろうが、その時に思い知らされる言語の必要性や、言葉を封じられた圧倒的な無力感は無念としかいいようがない。日頃、口数の少ない人ならまだ傷は浅いのかもしれないけれど、カウンターの中で、時には喉が枯れるほどに言葉に依存しているわたしにとって、自分の意思や表現が伝わらないことは、アイデンティティの揺るぎかねない死活問題と言ってもいい。つまり、わたしは重篤な言語依存人間なのである。
本書は、霊長類学者で人類学者でもある山極寿一さんと、小説家の小川洋子さんの対談で、人類がこれまでの進化の過程で獲得してきた能力(人間らしさ)と、霊長類(主にゴリラ)の生態を通じて語られる驚きの事実。そして、言語の獲得から言葉の持つちからの危険性と素晴らしさを教えてくれる。まさにタイトルにある「ゴリラの森、言葉の海」であり、これから人類が向かう未来について深く考えさせてくれる。
現在、猿や類人猿は三百種類の存在が認められているようだが、その中で人間とチンパンジー、オラウータン、ゴリラは、ヒト科と呼ばれているヒトの仲間で、遺伝子の組み合わせで人間と比較をしてみると、3%以下の違いしかないことに驚いた。その上で、人間だけがなぜここまで進化をとげたのか。
それは、ゴリラやオラウータンの祖先よりも人類の祖先の方が弱かったからで、熱帯雨林での生存競争から敗北し、命辛々サバンナに逃げ出したというのもおもしろい。人類の存亡を懸けた最初にして最大の「逃げるが勝ち」作戦は、数十万年をかけて結果を示した。逃げるが勝ちということわざは、人類最古の座右の銘なのかもしれない。それから人類は独自の進化を始め、陸の覇者となる。

現在は種族同士の争いが絶えないが、その理由は三つあって、言語を習得し嘘を覚えたこと、土地を持ち死者にリアリティーを与えたこと、共同体としての共感性を高めたことだという。たしかに、宗教の教理の相違や、領土をめぐる争い、国家間の利権の奪い合いなどの根底には、弱者であった人類が他の種族から根絶されないように獲得した種族保存本能が存在しているのだと思い知らされた。
森からサバンナへと逃れた人類の祖先は、肉食獣の的になった。そして多くの子供が餌食になったようだ。その過酷な環境だからこそ、人類は子供を増やさなくてはならなくなるのだが、その人体構造を何万年もかけて変異させていったのか、考えただけで途方もない。それは、子の離乳を早めさせ、母体のホルモンバランスを回復させ、短期間での多産を可能にした。ゴリラの出産は次の子を産むのに四年を有するようだが、人類は年子の出産を可能にしたようだ。
森の強者ゴリラは、四年を待たなければ新しい生命は誕生しない。子供は大切に育てられる。だが、オスゴリラには謎の習性があった。子殺しである。
ゴリラは、ボスゴリラを中心としてオスとメスが集団で生活を送る。
そこで突如として起こる子殺し。オスゴリラは、決してわが子は殺さず、他のゴリラの子を殺す。その理由は解っていない。その上で「私が切なく思うのは、子どもを殺された母親が、殺したオスと交尾をしてまた子どもを産むことです」と小川さんは述べているが、食物連鎖的にほかの動物に殺されるなら仕方が無いにしても、同種の大人が子を殺すオスの習性と、子の命を奪ったオスの子をその身に宿すメスの習性、いずれも想像に域をこえないようだが、その真の理由を知りたいものだ。
自分なりに想像を膨らませると、ゴリラが強者だったことに何か関係があったのかもしれない。その頃、人類の周囲は敵だらけで、種族を絶やさぬように生きなければならない弱者だった。同族の命を守ることはあっても奪うことなど考えもしなかったのだと思う。だがゴリラはその頃から森の強者だ。まるで、現在の人類が同種族で殺し合いをしていることに似ている。この本を読みながらそんな考察ができたことも実に有意義だった。

最後に、ゴリラは歌を唄いペットだって飼ってしまうユーモアや優しさがあり、時には暴君ともいうべき理解不能な行動もとるが、わたしには「古き良き昭和のオヤジ」のような印象が残り、彼らの存在がとても身近になったことは確かである。人間の進化は加速を続けながらどこへいってしまうのか。霊長類学者と小説家は慎重に警鐘を鳴らし、踏みとどまらせようとしている。
山極さんのこの言葉が突き刺さる。
「言葉の網ですくい切れないものがあふれている世界に、つい最近まで人間はほかの動物と一緒に暮らしていた。言葉に頼れば頼るほど、僕たちの世界はそれ以前に獲得した豊かな世界から離れていく。それは生物としての人間にとってあまりにももったいない損失なのではないか。(中略)ゴリラやサルと付き合いながら自然の森を歩いていると、生きることに意味などないような気になる。それぞれの生物に与えられた時間があり、それをあるがままに生きるのが生命の営みである」。
テクノロジーは不可能を可能にしていく。人類は分不相応な領域(神の領域)に入ろうとしている時代に、わたしは目の前のお客と会話を肴に酒を売る日々を過ごしている。しかし、語り合うことがより大切になってくるこの時代で、わたしの仕事は決して卑下するべきものではないのだと改めて気づかされる。よし、機会を作って、この素晴らしい対談の舞台ともなった屋久島にいってみよう。大自然の中で人間の生命も他の種族と何ら変わらないただの命に過ぎないことを実感するために。その時は、この本を持参し雄大な森の中で読み返してみようと心に決めた。わたしは「人間」であることにおごっていたのかもしれない。星の見えない東京の夜空を眺めながら、酩酊した頭でヒトであることをかみしめていた。
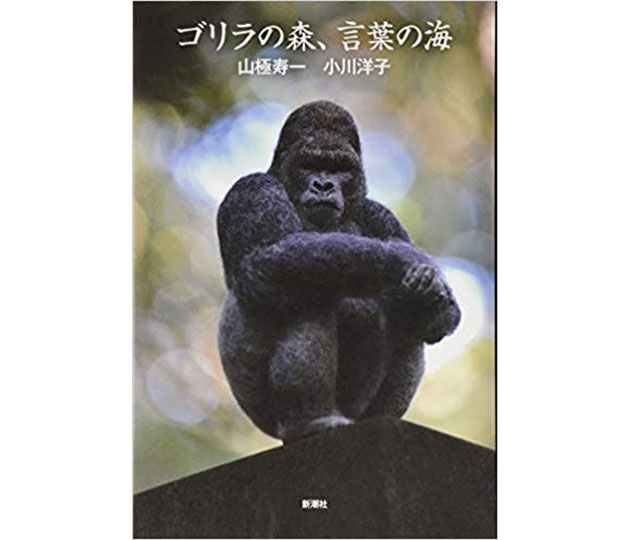
『ゴリラの森、言葉の海』新潮社
山極寿一、小川洋子/著

