2022/11/23
横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店
『はぐれんぼう』講談社
青山七恵/著

「はぐれんぼちゃん」
持ち主に忘れ去られた衣服のことをそう呼んだのは、同じクリーニング店で働く馬宵(まよい)さんだった。
随分遠くなってしまったその声が、彼方でこだまのように反響している。
まるで“わたし”をあるべき場所へと呼び戻そうとするように。
懐かしく響く声が導のように光るから。
わたしには帰らなきゃいけない場所がある。
夢のなかで、わたしは藤色のネクタイになっていた。
たしかに見覚えはあるのに、名前の思い出せない男性の首に巻かれたネクタイになった夢を見た。穏やかな心地で優しい気持ちに包まれながら、目覚めた優子はふと違和感を覚えた。
見るとネクタイだけではない、化繊のブラウス二枚が、ねずみ色のジャケットが、焦げ茶色のスラックスとセージのグリーンのスカートが、赤いチェックのマフラーが、わたしの体を覆っていた。
このような事態に見舞われると知っていたなら「はぐれんぼちゃん」を持ち帰るなんてことはしなかっただろう。けれど、やっぱり拒むことはできなかったのではないかとも思う。
店先に置かれた「おまかせ美人」と書かれた幟。誰にも気に留められず風に揺られるそれについて尋ねて来たお客さんを唯一の同志だと思った。
両親亡き後ささやかに暮らしながら、とらちゃんと名付けた猫を愛でる時間を心の支えにしていた。
馬宵さんに「あんたにはほんとうの心配事なんてないんでしょう」と言われるくらい呑気に見えていたとして、小さな幸福を大切に抱くように生きてきたのだ。
誰も引き取りにこない忘れ去られた存在は自分自身と重なるように思えた。
優子は「わたし」の分身のような、はぐれんぼちゃんを見捨てることができなかった。
とはいえ、幾重にも重なり脱ぐことすらままならないはぐれんぼちゃんと、いつもと同じ日常を送ることはできそうにもなかった。
馬宵さんに欠勤の連絡をした優子はぼんやりとこれからの行く末を思う。
しかし彼女の意志など関係なく、はぐれんぼちゃんたちに導かれるままに「持ち主たち」に会いにいく旅へと出発することになったのだった。
あるひとは「見ていると寒気がする」と言った。
あるひとは同僚を突き飛ばし、そのまま出口へと逃げるように駆けて行った。
はぐれんぼちゃんは持ち主の悲しい記憶や苦い思い出をたっぷりと吸い込んだまま、無きものにされているという悲しい現実が優子とともに取り残された。
予想外の顛末に気が沈む優子はしかし、はぐれんぼちゃんを脱ぎ捨てることがどうしてもできない。打ちひしがれる優子の背中を押してくれたのは意外にも、電話口から聞こえる馬宵さんの言葉だった。
あんたみたいに感情の平べったいひとが一番危ないんだよ。不安というものは赤ちゃんみたいなもんでね、月が満ちればこっちの都合なんか関係なく生まれてきちゃうものだから。
何も考えられなくなるくらい歩いて、歩いて、歩かなきゃあ
奇天烈な格好のままずんずん歩く。
その道すがら、優子と全く同じ具合に衣服に着られた男性と出合い、女性と出合い、夫婦に出合い、ともに「倉庫」を目指すことになる。
そもそもこれは、はぐれんぼちゃんが突然倉庫から大量に送り返されるようになったことから始まっているのだ。
その場所で、きっと何かが起こっている。
ひたすらに歩きながらも目的地の所在を知る者はない。
けれど、見慣れたピックアップ車を辿っていけばたどり着けるだろう。
野宿をした夜も、インターネットカフェで過ごした夜もあった。
コンビニのイートインスペースで慌ただしくした食事もあったし、住宅街で見つけたおいしいパン屋さんで焼き立てのフランスパンをほおばった朝もあった。
「日常」から逸脱し、出合った人々とともに過ごす時間は優子を大いに揺さぶった。
置き去りにされかけた時は過去の辛い記憶が蘇り、経験したことのない心身の疲労から諦めようと思ったのは一度や二度ではない。
持ち主に返せば容易く解決すると考えたその目論見は早々に打ち砕かれ、未知なる場所を目指す最中、「やめる」という選択肢は常に脳裏に浮かんでいた。
同時に、なぜ忘れてしまったのか。
赤いウールの編み地に数えきれないほどの小さな白いビーズが縫い付けられ、とても大切にしていたのに「サーカスみたい」と見知らぬ女子高生に言われてから、身に着けることが途端に恥ずかしくなってしまった。
今、こんな時に、いやこんな時だからこそ、あの懐かしく愛しい衣服をもう一度抱きしめたいと願う。
優子自身の「はぐれんぼちゃん」との思い出が、実は優子の足を動かしていたのかもしれない。
一目見たきりでは、それが倉庫だとは気づかなかった。
紆余曲折を経て、ようやくたどり着いた倉庫は明るいクリーム色をしていて巨大な食パンを想起させた。目印にしていた白いボックスカーが吸い込まれていくここが、目指していた場所であることは間違いなさそうだ。家を出てから四日半、自らの身体から立ち上がる匂いと鉛のような疲労がその道のりの壮絶さを物語っていた。
本音を言うと一刻も早くお風呂に入りたい。そして、泥のように眠りたい。
けれどここへとやって来たのは、「真相」を知るためなのだ――
あれ、でもなんだかおかしい。
ずるをして先に到着していた仲間のあまりのにこやかさに違和感を覚える。
そして、深く考える間もないままに湯舟のなかへと誘われてしまう。
これまでの思い出すべてがこのお湯のなかに一緒に溶け出し、地中に染み込んでいくのが分かる。ただひたすら、あたたかい、さらさらとした熱いお湯の渦に巻かれて、深い、深いところに……
穏やかな笑みを浮かべながら、ツヤツヤぴかぴか光る幸福そうな人々の言葉は、優子の芯を甘く痺れさせる。
「ここではどうぞ、あなたの好きなこと、得意なことを生かしてあなただけにできる仕事をして下さい。
憂いも懸念も、もうここでは生まれません。
万が一、再びそれらが襲いかかってきたのなら、
時間という概念も、世間というしがらみもここでは一切皆無なのです。
ここはみなが本当の自分に戻れる天国のような場所なんですから」
優子が今までの人生において培ってきた良きことも悪しきことも、ここで保ち持ち続けることはほとんど不可能だった。
微笑を絶やさぬまま、金銭の為でなく奉仕の精神でする仕事。
疲れたら心行くまで休んでいいなんて、夢みたいな理想の暮らし。
優子はここで言う「本当」に戻るためすべてを忘れてしまいそうになった。
しかし、この場所の本当の本当――
恐るべき秘密と犠牲によって、この場所は運営されていると知ってしまった。
私はこの物語は強烈なアンチテーゼを含む物語であると感じた。
現代社会への痛烈な批判。作り上げられた理想の裏側で排除された力なき人々。
寓話のような読みやすさと柔らかさで語られる物語は、気づけば辛辣な真実を目の前に差し出していて、逃げ出そうにももう手遅れだ。
読みながらずいぶん惑いもした。
輝かしい夢のように掲げた理想の世界にも、やっぱり「影」があると知りたくなかった。
揺れる感情を平らかにすることは、心を失くすことイコールであるかもしれないと思うほどに、伸ばし続けてきた手は行き場をなくして彷徨った。
結論は出そうにない。
答えはこの肉体から卒業するときにやっと分かるようなことなのだろうとも思う。
その一方で、波立つ心を抱えたままでいいんじゃないかという少しの諦めと、思いのほか清々しい気持ちを抱いていることもたしかなのだった。
成長と呼べる代物では決してない。
けれど、感情に振り回されながら、ままならない心と身体でこの世界をいっそう味わいたいと思ったのだ。
あなたがこの物語を読むことがあるのなら。
物語から何を受け取っただろう。どんな景色を見ただろう。
「答え」が分からない時こそ教えてほしい。
「正解」が消滅した後でこそ、見えた景色を伝えてほしい。
おわりの始まりに希望がやっぱりあっただなんて、
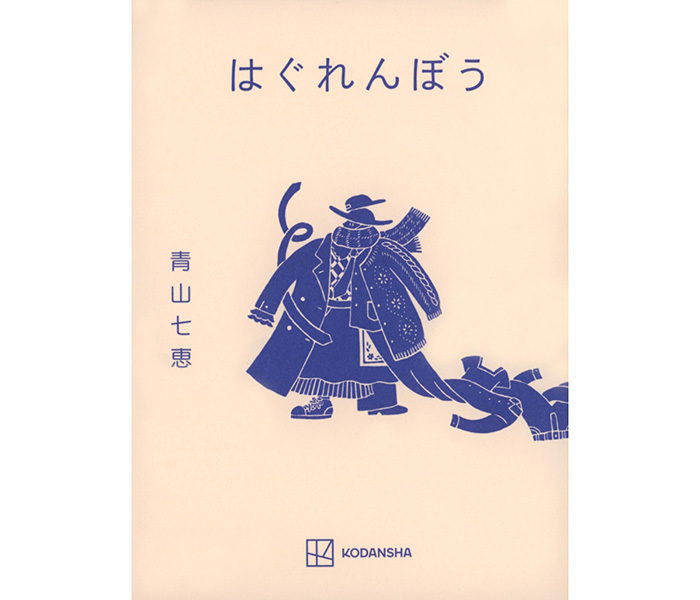
『はぐれんぼう』講談社
青山七恵/著

